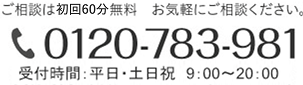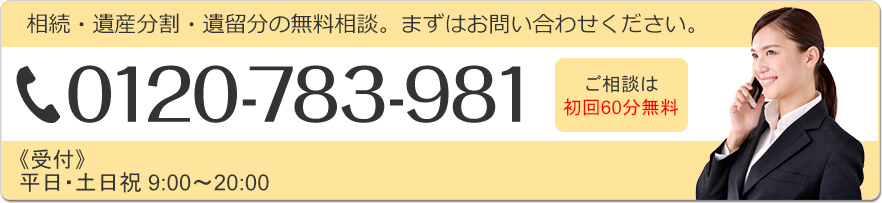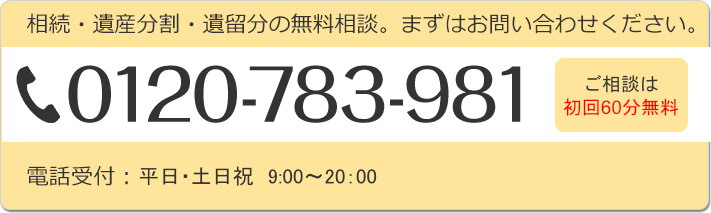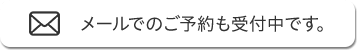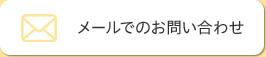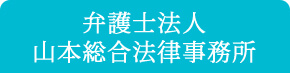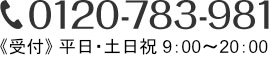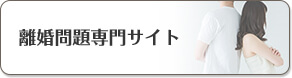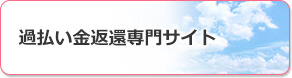生きているかわからない場合に相続できるの?
- 執筆者弁護士 山本哲也
1.生きているかわからない場合には

自然的死亡(医学的に死亡が確認された状態)によって相続が開始されるというのが一般的ですが、水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからないという場合があります。
このような場合に、その取調べにあたった役所(海上保安庁、警察署長など)が死亡の認定をして、戸籍上一応死亡として扱います。
本籍地の市区町村では、 死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨を記載します(戸籍法89条)。
これを「認定死亡」 といいます。
認定死亡によって、反証がなされない限り、戸籍記載の死亡の日に死亡したものと推定され、相続が開始し、また配偶者は再婚することができます。
それ以外にも、「失踪宣告」という制度があります(民法30条)。
2.失踪宣告とは

失踪宣告とは、人の生死が7年間明らかでないときに、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が宣告を行い、不在者について死亡と同様の法律効果を発生させる制度です(民法30条及び31条)。
死亡しているのか、それともどこかで生きているのかが分らない状況が続けば、家族が心配するだけでなく、不在者の財産等に関して利害関係を有する者の地位が不確定のままになってしまいます。
そこで、不在者の法律関係を確定し、利害関係人の法的地位を安定させることが必要になるのです。
失踪宣告によって失踪者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了し、また、相続が開始することになります(民法882条)。
失踪宣告には次の2つの種類があり、その条件が満たされた時に、失踪宣告がなされます。
- 不在者の生死が7年間不明の時(普通失踪。民法30条1項)。
- 戦地に行ったり、沈没した船舶に乗船していたりするなど、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死が不明の時(特別失踪あるいは危難失踪。民法30条2項)。
申立てを受けた家庭裁判所は調査を行った上で、不在者には生存の届出をするように、不在者の生存を知っている者にはその届出をするように催告をし、その期間内に届出がなければ失踪の宣告がなされます。
不在者本人、利害関係人による即時抗告がなければ、失踪宣告は確定します。
不在者は、上記①の場合は7年間が満了した時、上記②の場合は危難が去った時に死亡したものとみなされ(民法31条)、その時点で相続が開始されます。
3.失踪宣告が必要な状況

遺産分割は相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。
実際には、遺産分割協議を行うという段階になって、相続人の一部が行方不明であることが判明するという場合が少なくありません。
このような場合、行方不明となっている相続人について何らかの対応を行った上で遺産分割協議を進めないと、協議終了後に行方不明者が登場して遺産分割の無効を主張すれば、遺産分割をやり直さなければならなくなります。
行方不明となっている相続人について、他の相続人は、利害関係人は失踪宣告を申し立てることができます。
上記で述べた要件が満たされていれば、失踪宣告により、行方不明となっている相続人は死亡したものとみなされます。したがって、行方不明となっている相続人を相続する者がいる場合にはその者を加えて、相続をする者がいない場合には行方が判明している相続人だけで遺産分割をすることができます。
なお、失踪宣告の要件が満たされている場合であっても、失踪宣告の申立てをせず、以下に述べる不在者財産管理人を選任して、行方不明となっている相続人に代わって遺産分割を行わせることもできます。
4.失踪宣告までの間に遺産分割を行いたい場合

普通失踪の場合は失踪から7年、特別失踪の場合は危難が去ってから1年が経過するまでの間は、不在者は死亡したとはみなされないため、その間は遺産分割をすることができないことになります。
しかし、その場合には、失踪宣告の申立てではなく、これからご説明する不在者の財産管理人選任申立ての方法を取ることができます。
行方不明となっている相続人が生死不明であったとしても、失踪宣告の要件を満たさない場合や(民法30条1項)、生きていることは分かっているものの、所在が知れないというような場合には、利害関係人が家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てます(民法25条1項)。
不在者財産管理人は、原則として、不在者の財産を管理、保存する権限しか持っていません。遺産分割は不在者の財産の管理、保存には該当しないため、不在者財産管理人と共に遺産分割を行うためには、家庭裁判所から、権限外行為許可を得る必要があります(民法27条、28条)。
選任された不在者財産管理人が、行方不明となっている相続人に代わって遺産分割協議に加わることにより、相続人が全員出席した上で遺産分割協議を行った場合と同様に扱われます。
5.失踪宣告が取り消された場合

相続においては、行方不明者が失踪宣告を受けるとその者は死亡したものとみなされます(民法31条)から、その者につき、相続が開始されます。
しかし、後でその失踪者が生きていることが明らかになれば、その者を死亡したものとして取扱うのは不合理です。
そこで、本人又は利害関係人の請求によって、家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことになります(民法32条1項)。
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告はなかったことになり、原則として財産関係や身分関係が元通りに復活します(民法32条1項1文、同条2項本文)。
ただし、宣告が取り消された場合でも、混乱を避けるため、
- 失踪者が生きていたことを知らないでした相続財産の処分などの行為は有効です(民法32条1項後段)。
- 相続人など、失踪宣告により直接的に財産を得た者は、失踪宣告の取消しにより財産についての権利を失いますが、その利益が残っている限度で失踪者に返還すればよいとされています(民法32条2項ただし書)。
6.失踪宣告については専門家に相談を

普段から親戚間で連絡を取っている方にとっては相続人が生きているかどうかがわからないという状況は考えにくいかもしれません。しかし、弁護士に依頼することで、今まで全く連絡は取り合ってこなかった相続人の存在が戸籍から発見される可能性があります。相続人の一部を関与させずに遺産分割協議を進めても、その協議は無効となってしまい、時間の無駄に終わってしまいます。そのため、相続人の調査など早い段階から弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。
7.群馬、高崎で遺産相続・遺留分請求に強い弁護士なら山本総合法律事務所

群馬、高崎で相続トラブルを相談するなら、相続案件に強く群馬や高崎の地元の特性にも精通している弁護士を選びましょう。相続を得意としていない弁護士に依頼しても、スムーズに解決しにくく有利な結果を獲得するのも難しくなるためです。
山本総合法律事務所の弁護士は、設立以来、群馬や高崎のみなさまからお悩みをお伺いして親身な対応をモットーとし、満足頂ける結果を提供し続けてまいりました。
群馬、高崎にて遺産相続にお悩みの方がいらっしゃったら、ぜひとも山本総合法律事務所までご相談ください。