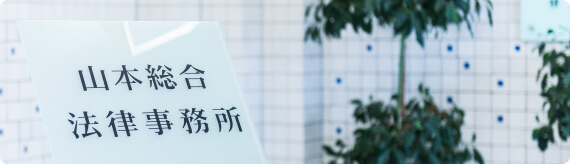目次
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)の本来の相続人が、相続開始(死亡時)以前に死亡したり、相続権を失っていた場合に、その子や孫、甥・姪などが代わりに相続人となる制度です(民法887条2項本文・899条2項)。
本来の相続人を「被代襲者」、代わって相続する人を「代襲相続人」と呼びます。
この制度は、相続権がある人が先に亡くなっていても、その子孫に権利を受け継がせることで、家族関係や相続の公平性を維持することを目的としています。
代襲相続が発生する3つのケース
代襲相続は、被相続人の「子」または「兄弟姉妹」が相続権を失っている場合に、その子どもなどが代わりに相続人となる制度です。では、どのような場合に代襲相続が発生するのでしょうか。主に次の3つのケースが挙げられます。
①被相続人より先に相続人が死亡している場合
被相続人が亡くなる前に、本来の相続人がすでに他界していた場合、代襲相続が発生します。
また、被相続人と相続人が同時に死亡(例えば同一の事故など)した場合も、相続人が被相続人の死亡時に生存していないため、代襲相続が認められます。
②相続人が相続欠格となっている場合
相続欠格とは、相続人に重大な非行があった場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。
このような場合も、代襲相続が発生します。
相続欠格となる主な行為には、以下のようなものがあります。
-
被相続人や他の相続人を故意に死亡させる、または死亡させようとした
-
被相続人を脅して不利な遺言を書かせた
-
遺言書を偽造・破棄・隠匿した など
民法第891条(相続人の欠格事由)
相続欠格の具体的な内容は、以下の条文に定められています。
民法 第891条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者【出典】e-Gov:民法第八百九十一条
相続欠格が適用された場合は、被相続人の意思にかかわらず、その相続人は相続権を失います。
③相続人が相続廃除されている場合
相続廃除も、相続権を失う原因の一つであり、これに該当する場合も代襲相続が発生します。
相続廃除とは、推定相続人が被相続人に対して著しい非行を行った場合に、家庭裁判所の手続きを経て相続権を失わせる制度です。
主な対象行為は以下のとおりです。
-
被相続人に対する虐待や重大な侮辱
-
被相続人の財産を著しく損なう行為(浪費、借金を負わせた等)
民法第892条(推定相続人の廃除)
この制度は、被相続人の申立てによって実行されます。また、遺言によって廃除の意思を示すことも可能です。
民法 第892条 (推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
【出典】e-Gov:民法第八百九十二条
遺言による相続廃除の場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば廃除が成立します。
こうして相続権を失った相続人に代わり、代襲相続が発生するのです。
代襲相続が認められないケースとは?
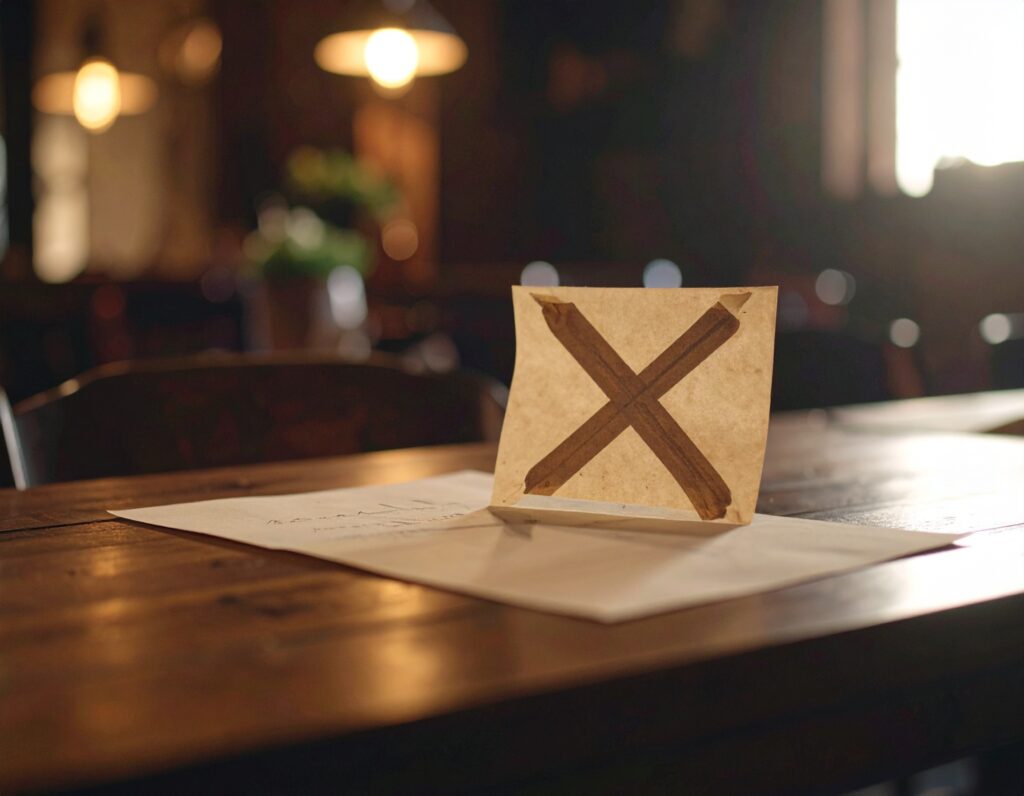
以下のような場合には、代襲相続は認められません。
- 相続放棄があった場合
- 被相続人より後に相続人が死亡した場合
- 遺言で指定された人が先に亡くなっていた場合
- 甥・姪の子ども
- 養子縁組前に生まれた養子の子
- 配偶者の連れ子
各ケースについて、以下で説明します。
1.相続放棄があった場合
相続放棄が行われた場合、その相続人に代わって代襲相続が発生することはありません。
相続放棄とは、被相続人の財産や債務を一切引き継がないことを意味します。
相続放棄をすると、法律上は最初から相続人でなかったものとみなされます。したがって、相続権自体がなかったことになり、その子などが代襲して相続することも認められません。
【参考】相続放棄とは
2.被相続人より後に相続人が死亡した場合
相続人が被相続人の死後に亡くなった場合は代襲相続にはなりません。
この場合は「数次相続」として扱われます。
3.遺言で指定された人が先に亡くなっていた場合
遺言で遺産を受け取るとされた人が、遺言者よりも前に死亡していた場合、その人への遺贈は無効となり、代襲相続も発生しません。
回避するには予備的な記載が必要です。
【参考】遺言書の作成
4.甥・姪の子ども
兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
甥や姪がすでに死亡していても、その子(被相続人にとっての大甥・大姪)には代襲相続権はありません。
5.養子縁組前に生まれた養子の子
養子縁組よりも前に生まれた養子の子は、養親との法律上の親子関係がないため、代襲相続は発生しません。
養子縁組後に生まれた子であれば可能です。
【参考】養子に相続はできるのでしょうか?
6.配偶者の連れ子
代襲相続は被相続人の「子」または「兄弟姉妹」に限定されており、配偶者の連れ子には発生しません。
遺産を渡したい場合は、遺言や養子縁組などの対応が必要です。
数次相続との違い
代襲相続とよく混同されがちなのが「数次相続」です。
代襲相続と数次相続の違いは、相続人となる人が亡くなった順番の違いです。
数次相続とは?
被相続人の相続が始まった後、遺産分割が完了する前に相続人の一人が亡くなり、その相続人についてさらに相続が発生することです。
代襲相続は「生きていれば相続人だった」人の子どもがその人に代わり相続人になる、という状態です。
代襲相続と数次相続の違い
それぞれの特徴をまとめると、下記の通りです。
| 項目 | 代襲相続 | 数次相続 |
|---|---|---|
| 発生の時期 | 最初の相続開始時に発生 | 最初の相続発生後、相続人が死亡して発生 |
| 必要な相続手続 | 一回の手続きで済む | 複数回の相続手続きが必要 |
| 典型的なケース | 子が被相続人より先に死亡し孫が相続する | 子が遺産分割前に死亡し、その子が相続する |
| 再代襲の有無 | 一定条件で可能(直系卑属のみ) | 各相続ごとに個別の相続が発生 |
誰が代襲相続人になれる?

代襲相続人になれるかどうかは、被代襲者との関係によって異なります。主に以下の2つのケースが想定されます。
①直系卑属の場合(子・孫・ひ孫)
被相続人の子がすでに死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人になります。
さらに孫も亡くなっている場合には、ひ孫が相続することもできます。これを「再代襲」といいます。
②兄弟姉妹の場合(甥・姪)
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。
ただし、このケースでは再代襲は認められません。
法定相続人ごとの代襲相続の有無
法定相続人のうち、代襲相続人になれる人をまとめると次の通りです。
| 本来の相続人 | 代襲相続の対象 | 再代襲の可否 |
|---|---|---|
| 子 | その子(孫) | あり(ひ孫) |
| 兄弟姉妹 | その子(甥姪) | なし |
再代襲相続とは?
再代襲相続とは、代襲相続人がすでに死亡している場合に、その子がさらに相続を引き継ぐ制度です。
これは、直系卑属に限って認められている制度です。
再代襲相続の例
- 被相続人Aの子Bがすでに死亡 → 代襲相続人はBの子C(孫)
- さらにCもすでに死亡 → 再代襲相続人はCの子D(ひ孫)
このように、直系卑属の相続では、世代を超えて相続権が引き継がれることがあります。
再代襲が認められないケース
なお、兄弟姉妹を通じた代襲(甥・姪)については、再代襲相続は認められていません。
代襲相続人の相続分
代襲相続人は、被代襲者が本来取得する予定だった相続分をそのまま受け継ぎます。
これは「代襲」という性質に基づき、親の立場を子がそのまま引き継ぐという考え方によります。
基本的な分け方
相続人全体の相続分は、法定相続に従って配分されますが、代襲相続が発生する場合は、被代襲者が得るはずだった割合を、代襲相続人が人数に応じて分け合う形となります。
【参考】誰が相続人になれるか、どれくらい遺産をもらえるかを教えて欲しい ~法定相続について弁護士が解説~
相続分の具体例
| 続柄 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者+子1人 | 配偶者1/2、子1人1/2 |
| 配偶者+子1人(死亡)+孫2人 | 配偶者1/2、孫2人で1/2(各1/4) |
| 配偶者+子1人(死亡)+孫1人 | 配偶者1/2、孫1人で1/2 |
計算時のポイント
- 代襲相続人が複数いる場合は、原則として均等に分割されます。
- 被代襲者が複数の子を持つ場合などは、人数で割る計算が必要です。
遺産分割の前におさえておくべき重要ポイント

これまで、代襲相続人になれる対象や相続分について説明してきましたが、実際に代襲相続が発生すると、遺産分割の手続きが複雑になることがあります。
そのため、遺産分割を行う前に押さえておきたい代襲相続に関する重要なポイントを、以下の3つに分けて解説します。
-
代襲相続人が加わっても、他の相続人の取り分には影響しない
-
代襲相続人の関係性によって遺留分の有無が異なる
-
遺言による遺贈には代襲相続が適用されない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①代襲相続人が加わっても他の相続人の相続分は変わらない
代襲相続人がいる場合でも、既存の相続人の相続分が減ることはありません。
すでにご説明したとおり、代襲相続人は本来の相続人が有していた相続分をそのまま受け継ぎます。仮に代襲相続人が複数人いたとしても、その相続分を均等に分け合う形となり、他の相続人の取り分には一切影響しません。
【参考】相続の配分について
②続柄によって遺留分が認められるかどうかが決まる
代襲相続人は、原則として本来の相続人の権利を引き継ぎますが、遺留分については注意が必要です。
民法では、遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」と定められており、具体的には配偶者・子・直系尊属(親)などが該当します(民法第1042条)。
民法 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。【出典】e-Gov:民法第千四十二条
このため、孫や曾孫といった直系卑属が代襲相続人になった場合には遺留分が認められますが、甥や姪が代襲相続人となった場合には遺留分は発生しません。
遺留分とは?
遺留分とは、遺言によっても奪うことができない、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
たとえ遺言で別の指定があっても、遺留分を下回る場合は「遺留分侵害額請求」をすることで不足分を取り戻すことが可能です。
なお、孫が代襲相続人になる場合の遺留分は、法定相続分の1/2です。
【参考】遺留分の基本
③遺言による遺贈には代襲相続が適用されない
被相続人が遺言で財産を特定の人に贈る(遺贈)旨を記していたとしても、その受遺者が遺言者の死亡前に亡くなっていた場合、遺贈の効力は生じません(民法第994条)。
民法 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。【出典】e-Gov:民法第九百九十四条
このように、法定相続とは異なり、遺贈においては代襲相続が認められず、受遺者が先に亡くなっている場合は、別途受遺者を指定していない限り、遺贈の効力そのものが失われることになります。
【参考】遺贈について ─遺贈の種類、適したケース、トラブルを避ける方法を解説─
相続税の計算における注意点

相続税の申告においても、代襲相続人が増えると法定相続人の数が変わるため、基礎控除額などが変動します。
相続税の基礎控除額は、以下のように相続人の人数によって決まります。
| 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
基礎控除額の計算例
- 相続人:配偶者+次男+孫2人(代襲相続人) → 計4人
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円×4 = 5,400万円
上記のケースでは、基礎控除額は5400万円となります。
そのため、遺産の総額が5400万円を超える部分については相続税が発生します。
このように代襲相続が発生すると基礎控除額も変動する可能性があり、慎重な判断が必要となりますので、専門家に相談されることをおすすめします。
代襲相続で起こりうるトラブル
代襲相続が発生すると、相続手続きがより複雑になり、さまざまなデメリットが生じることがあります。以下に主な点をまとめます。
相続人の数が増え、手続きが煩雑になる
代襲相続が発生すると、本来1人だった相続人がその子どもや孫など複数人に分かれるケースが多く、相続人の人数が増加します。
その結果、次のような不都合が生じます。
-
遺産分割協議の合意形成が困難になる
-
印鑑証明や戸籍の収集といった手続きの手間が増える
-
全員の連絡・調整に時間がかかる
【参考】相続人調査や戸籍の収集方法
相続分が細分化されてしまう
代襲相続では、被代襲者(本来の相続人)の相続分を代襲相続人全員で按分するため、1人あたりの取り分が非常に少額になることがあります。
-
例えば、本来の相続人が1/4を受け取るはずだったところに、その子が3人いれば、1/12ずつになります。
-
少額の持ち分が分散されると、不動産の共有などで後の処分・管理が難しくなります。
相続人の所在不明・連絡困難が起こりやすい
代襲相続人が遠方に住んでいたり、面識がなかったりする場合もあるでしょう。
そのため、以下のような問題が起きる可能性があります。
-
連絡先の把握や書類のやりとりに時間がかかる
-
所在不明者がいる場合、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任が必要になる可能性もある
【参考】相続人が遠方に住んでいる場合、どのように遺産分割をすすめればよいですか?
感情的な対立が起きやすい
代襲相続人は、他の相続人から見ると疎遠な親族であることが多く、「なぜあの人が相続人に?」という感情が生じやすいです。
-
特に、被代襲者と他の家族との関係が悪かった場合、その子や孫への感情にも影響することがあります。
-
相続分の主張でトラブルになるリスクが高まります。
【参考】相続紛争とは?トラブルになりやすいケースや紛争を起こさない方法について弁護士が解説
代襲相続でトラブルにならないための対応策

代襲相続が発生した場合すると、相続手続きの煩雑さや相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。
トラブルを回避・軽減するための対応策を以下に整理してご紹介します。
1. 遺言書の作成(特に公正証書遺言がおすすめ)
まず有効な対策として挙げられるのが、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことです。
遺言書によって、誰にどの財産を相続させるかを明確に指定しておけば、代襲相続が発生した場合でも遺産分割協議を行う必要がなくなるケースがあります。
特に公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認も不要で、よりスムーズに相続手続きを進めることができます。
また、代襲相続を想定して、遺言書の中に「遺贈先が先に亡くなっていた場合の予備的な相続人(予備的受遺者)」を指定しておくことで、不要なトラブルを防ぐことが可能です。
具体策
-
「長男が亡くなっていた場合、その配偶者や子には遺産を渡さず、次男にすべての財産を相続させる」などの文言を入れて公正証書遺言を作成する
注意点
遺言書によって代襲相続人に相続させない内容とする場合には、その代襲相続人が遺留分を持つかどうかに注意する必要があります。
代襲相続人が甥や姪である場合、民法上、遺留分は認められていないため、甥や姪には遺留分侵害額請求をする権利がありません。
一方で、代襲相続人が孫など、直系卑属にあたる場合は、法律上、遺留分が保護されています。
このような代襲相続人を遺言によって排除し、他の相続人にすべての財産を与える内容とした場合には、遺留分を侵害してしまうおそれがあります。
その結果、代襲相続人から遺留分侵害額の請求を受ける可能性があるため、遺言を作成する際には十分な配慮が求められます。
【参考】遺留分の請求をされないために
2. 遺産分割協議の早期開始と「まとめ役」の選出
代襲相続が発生すると相続人の数が増え、面識のない人同士が協議に参加することも珍しくありません。
そのため、早い段階で全相続人と連絡を取り、協議の窓口となる代表者を1人定めておくと、手続きが円滑に進みます。
代表者が中心となって調整や情報共有を行うことで、合意形成にかかる時間や労力を減らすことができます。
具体策
-
遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要なため、早めに全員と連絡を取り、話し合いの窓口となる代表者(相続人の中から信頼できる人)を決める
-
共有状態になる財産(特に不動産)は「現物分割」や「換価分割」などを検討
【参考】不動産の遺産分割方法3種類
3. 相続関係説明図と戸籍調査の早期対応
代襲相続人が孫や甥姪など複雑な関係にある場合、誰が法定相続人なのかを明確に把握するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、家系図を整理しておく必要があります。
この作業を怠ると、協議の前提自体が不明確になり、無効な手続きとなる恐れもあります。
具体策
-
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
-
相続関係説明図(家系図)を作成して全体像を把握
【参考】相続人調査や戸籍の収集方法
4. 専門家の活用(弁護士・税理士・司法書士)
弁護士は相続人同士の間で意見の対立があった場合に調整役として機能し、法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートします。税理士は相続税の申告や評価、特例適用の判断などで専門的な助言を行い、司法書士は不動産の名義変更や必要書類の整備を迅速に進めてくれます。
各士業の役割の違い
各士業の役割をまとめると下記の通りです。
代襲相続で遺産分割の進行に不安があったり、トラブルが起きてしまった時は弁護士に任せると安心です。
| 項目 | 対応できる内容 |
|---|---|
| 弁護士 | 複雑な相続関係や意見の対立がある場合に調整・代理交渉を依頼できる |
| 税理士 | 相続税の申告・配分のアドバイス |
| 司法書士 | 不動産名義変更や相続関係説明図の作成 |
5. 家族信託などの生前対策
被相続人が生前に財産の承継方法を明確に設計しておきたい場合は、家族信託の活用も一つの選択肢です。
家族信託は、生前に信託契約を結ぶことで、自身の財産を信頼できる家族に託し、どのように管理・承継していくかをあらかじめ決めておく制度です。これにより、亡くなった後の相続手続きを簡素化し、代襲相続による不確実性を抑えることが可能となります。
具体策
-
被相続人が元気なうちに「家族信託契約」を結ぶことで、死後の遺産承継に柔軟性と安心感を持たせられる
-
共有不動産を1人に集中させるなど、処分や管理のしやすさを確保
代襲相続のトラブルは弁護士に相談を
代襲相続は、被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていた場合に、その子(孫や甥・姪など)が代わりに相続人となる制度です。一見すると公平な仕組みに思えますが、実際の相続手続きでは、この代襲相続が原因で思わぬトラブルが生じることがあります。
たとえば、代襲相続人が複数いることで相続人の数が増え、遺産分割協議がまとまらない、連絡が取れない親族がいる、遺留分の主張をめぐって対立が起きるなど、話し合いだけでは解決できないケースも少なくありません。特に、被相続人と生前に関係の薄かった代襲相続人が登場する場合、他の相続人との間で感情的な対立に発展することもあります。
こうした複雑な相続問題に直面したときには、弁護士に相談することが最も確実で安心な対応策です。
弁護士は、法律に基づいて相続人の範囲や相続分を正確に判断し、必要な手続きを的確に進めてくれます。また、相続人間の調整役として、遺産分割協議を円滑に進めるためのサポートも行います。
代襲相続に関するトラブルを放置してしまうと、相続が長期化したり、家庭内の関係が悪化するリスクもあります。少しでも不安を感じたら、早めに弁護士にご相談ください。相続に精通した弁護士であれば、あなたの状況に応じた最適な解決方法のご提案が可能です。