ご依頼から約5か月で遺留分侵害額として3000万円が支払われたケース

ご相談内容
遺留分侵害額請求
解決方法
交渉
相続人
子供2人(長男・長女)
被相続人との関係
子
相続財産
不動産(被相続人の自宅)、預貯金、株式
ご相談の経緯
「すべての遺産を長男に相続させる」と記載された公正証書遺言が見つかり、被相続人の死後、依頼者(長女)は自分の遺留分が侵害されているのではないかと疑問を抱き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談の中で依頼者は、「父の相続のときには弁護士を付けずに自分で対応したが、スムーズに話が進まず苦労した経験がある。今回は専門家にしっかり対応してもらいたい」と話されており、その場で正式にご依頼をお受けする運びとなりました。

解決までの流れ
まずは、遺産の全体像と評価額を把握する必要がありました。遺言によって遺産のすべてを相続していた長男が、相続税の申告を済ませていると考えられたため、当職から長男に対して内容証明郵便で通知を送付し、以下の対応を求めました。
・遺留分侵害額請求を行う旨の通知
・相続税申告書および申告時に使用した資料一式の開示
その後、長男からは当方の請求に応じて必要な資料一式が提出されました。
これにより、当事務所にて相続財産の評価額をもとに遺留分侵害額を具体的に計算し、改めて長男に対して金額を明記した正式な請求を行いました。
対応結果
当方からは、相続財産の評価根拠や計算方法を明確に記載した書面を提出し、法的根拠に基づいた遺留分侵害額として3,000万円を請求しました。その結果、当方の主張がほぼ認められ、長男から3,000万円の支払いを受けることで合意に至りました。特に大きな争いや紛争に発展することなく、協議ベースで円満に解決した事案となりました。
解決までの期間
当事務所への正式なご依頼から解決に至るまでの期間は、約5か月でした。







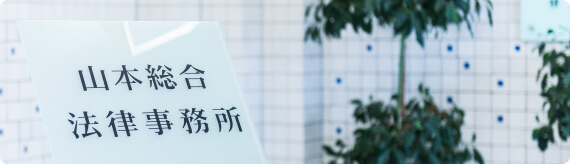


担当弁護士からのコメント
本件では、依頼者の手元に相続財産の資料がほとんどなかったため、まずは相手方(長男)から相続税申告時の資料を取り寄せたうえで、財産の内容と評価を整理し、遺留分侵害額を計算・請求するという段取りとなりました。
そのため解決までに一定の時間を要しましたが、相手方との交渉は比較的スムーズに進み、法的な主張に基づいた説明を丁寧に行うことで、ほぼ請求額通りの金額で合意に至ることができました。
相続人同士で直接話し合う場合、法的には大きな争点がない場合でも、過去の家族間の感情や経緯により、話し合いが難航するケースは少なくありません。特に、特定の相続人だけが大きな財産を取得するような遺言が存在する場合、他の相続人が不満を持ちやすく、感情的な対立が起きやすい傾向があります。
そのような状況では、弁護士が第三者として間に入り、法的根拠に基づいて冷静かつ合理的に交渉を進めることで、当事者間の感情的な衝突を回避し、早期かつ円満な解決に導くことが可能となります。本件もまさにその典型的なケースであり、早期の弁護士介入によってスムーズに解決した一例といえるでしょう。