高圧的な次男との交渉を避け、相続分譲渡と調停で早期かつ有利に解決した事例

ご相談内容
遺産分割
解決方法
調停
相続人
3人(子2人、妻)
被相続人との関係
妻
相続財産
不動産(被相続人の自宅)、預貯金
ご相談の経緯
ご相談にいらしたのは、亡くなられたご主人の妻である70代の女性でした。ご主人のご逝去後、相続の手続きを進めようとしたところ、次男が一方的かつ高圧的な態度で遺産分割についての話を進めようとしてきたため、大きな不安を感じておられました。
「このままでは冷静な話し合いにならず、言いなりになってしまうかもしれない」
「できれば、直接やり取りをせずに専門家に間に入ってもらいたい」
そういったお気持ちから、当事務所にご相談をいただき、そのままご依頼をお受けすることとなりました。

解決までの流れ
【当事務所の対応】
まずは遺産の内容を確認するため、詳細な財産調査を行いました。すると、ご主人が生前に次男へ数十万円の金銭を渡していた記録が見つかりました。これが「特別受益(生前贈与)」に該当する可能性があったため、当方としてはその点を主張材料として組み立てることにしました。
次男に対しては、まず受任通知を送付して正式に交渉の窓口が弁護士に切り替わったことを伝えましたが、残念ながら一切の回答がありませんでした。そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる運びとなりました。
【相続分譲渡の工夫と調停での進行】
遺産分割調停を申し立てる際は、原則としてすべての相続人を相手方として手続を行う必要があります。しかし、本件では依頼者と対立していたのは次男のみで、長男・長女とは協調的な関係が築けていました。
そこで、依頼者を「相続分の譲受人」、長男・長女を「譲渡人」として、相続分譲渡の手続を行うことで、実質的に次男のみを調停の相手方とすることができるようにしました。これにより、調停手続を簡素化し、対立のある次男とのみ集中的に話し合いを進めることが可能となりました。
【解決のポイントと結果】
調停において、次男は生前贈与(特別受益)については認めないという姿勢を崩しませんでした。しかし、不動産の評価額などその他の重要な争点については当方の主張に反論せず、一定の合意が見込まれる状況となりました。
仮に「特別受益」にこだわって主張を続けた場合、不動産の評価をめぐってさらなる争いが起こり、かえって依頼者にとって受け取れる財産が減る可能性もあるというリスクがありました。
そのため、第1回調停期日で「特別受益の主張は取り下げる代わりに、不動産の評価額は当方の主張を前提とする」という形で、調停をまとめる方向に舵を切りました。結果的に、依頼者にとって有利な内容で調停が成立し、約6か月という短期間での早期解決が実現しました。








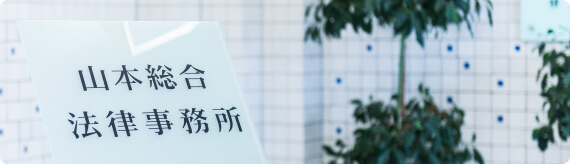


担当弁護士からのコメント
相続は、法律的な手続きの問題であると同時に、「家族との関係」や「感情」が大きく絡んでくる場面でもあります。
今回のように、ある相続人の方が高圧的な態度を取ったり、話し合いがうまく進まないというケースは、実は決して珍しくありません。
「本当は穏やかに話し合いたいのに、感情的に押し切られそうで怖い」
「言い返すこともできず、結局言われるがままになってしまいそう……」
そういった不安やストレスを抱えながらも、誰にも相談できず、一人で悩んでいる方は少なくないのではないでしょうか。
私たちは、そうしたお気持ちに寄り添いながら、専門的な知識と手続きを通じて、ご依頼者さまの立場を守るお手伝いをしています。
今回のケースでも、相続分譲渡といった少し特殊な手続きを用いることで、依頼者さまが直接対立する相手と向き合うことなく、落ち着いて解決に向けた道筋をつけることができました。
相続の話し合いは、一度こじれてしまうと関係の修復が難しくなることもあります。だからこそ、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
法的にどのような選択肢があるのか、どんな手段をとればご自身にとって有利なのか。冷静に、そして公平に考えるためのサポートを、私たちは惜しみません。