
ご相談内容
遺産分割
解決方法
財産・相続人調査、交渉
相続人
8名
被相続人との関係
姉弟
相続財産
不動産、預貯金等
ご相談の経緯
姉弟が亡くなり、自分を含む兄弟姉妹が遺産を相続することになったが、既に亡くなっている人もおり、その場合の相続人や分割方法等について相談したいとのことでいらっしゃいました。
相続人の範囲や今後の流れ等をご説明しましたが、あまり交流のない相続人もおり、自身で処理することが困難などの事情により依頼となりました。
【参考】相続人が15名、行方不明者もいたものの、弁護士に依頼して無事に遺産分割を終えた事例

解決までの流れ
まず、相続人及び遺産を調査する必要がありましたので、両者の調査を行いました。
特定後は、すぐに各相続人と連絡を取り、遺産分割について説明等を行い、分割案について協議・交渉を行いました。
協議成立後は、遺産分割協議書を作成、協議書に従って遺産を分配し、無事終了となりました。
【参考】【書式つき】遺産分割協議書の書き方をパターンごとに弁護士が解説!








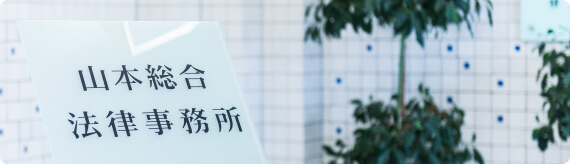


担当弁護士からのコメント
本件は、相続人の中にご高齢の方が複数名(80代後半や90代)いらっしゃいました。
ご高齢の方がいらっしゃる場合には、認知症などにより意思能力に影響が出ていることが懸念されるところであり、依頼者からも意思疎通が難しい方がいるかもしれないと伺っておりましたので、程度によっては後見人の選任も想定しておりました。
もっとも、皆様お元気で意思能力に特段問題ありませんでしたので、スムーズに協議・交渉を行うことができました。
また、依頼者以外の相続人の方々については県外に居住しておりました。
遺産分割協議書は、1通の書類に全相続人が署名・押印する形式を取ることが多いものと思いますが、本件のように相続人が遠方に居住していたり、多数におよぶ場合には、上記方法により書面を作成すると非常に時間がかかってしまいます。
また、署名・押印に誤りがあると、最悪の場合、最初から書面を作成し直さなければならなくなります。
このような場合には、同一内容の協議書を各相続人分作成し、1通の書面に1人の相続人の署名・押印をしていただく方式を選択するとよいでしょう。
協議書完成までの時間を短縮できますし、仮に誤りがあってもその相続人分のみ再作成等すればよくなります。
本件も本方式を採用し、1~2週間程度で協議書の作成が完了し、登記や預貯金の解約等の手続きが滞りなく行われました。
【参考】遺産相続を弁護士に相談すべき11の状況
遺産分割を弁護士に依頼するメリット