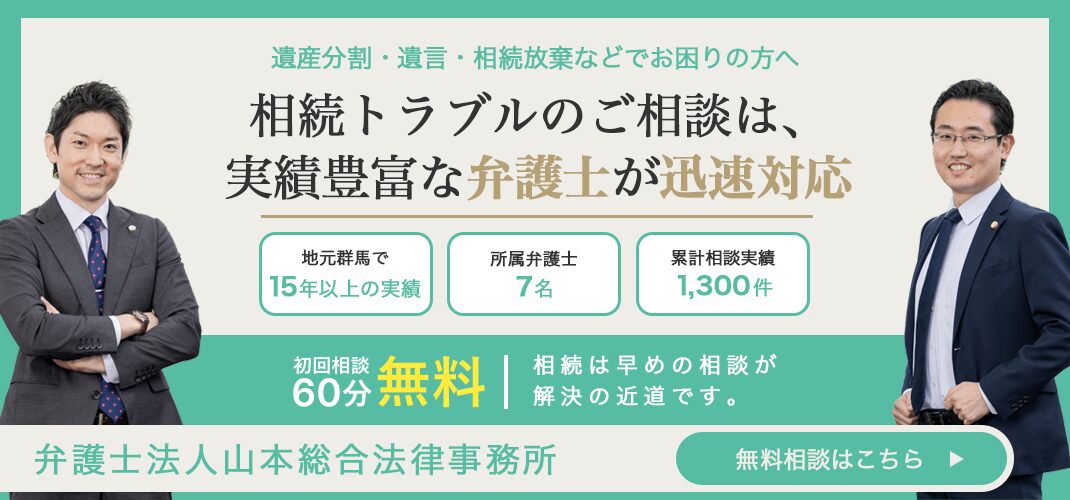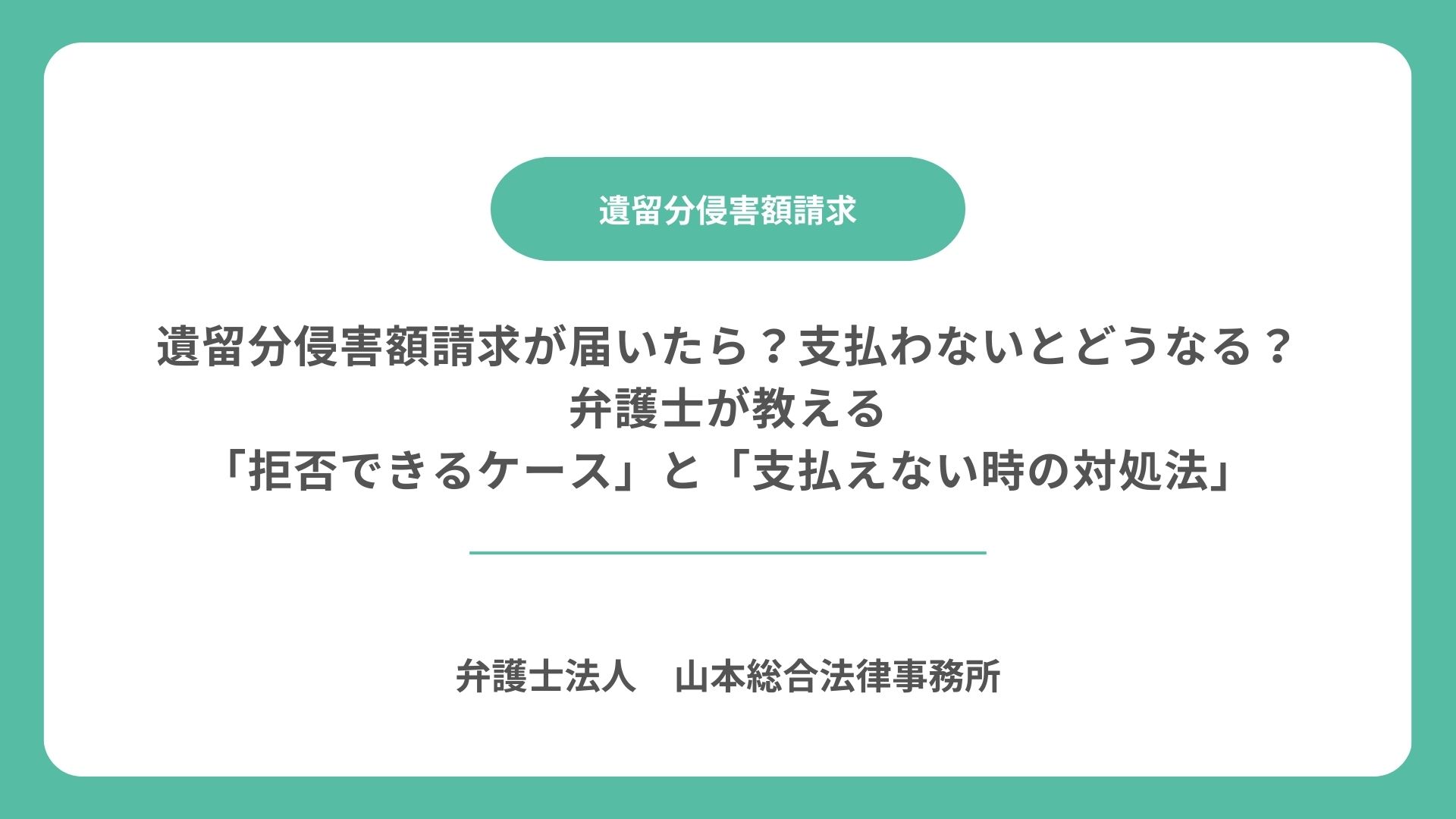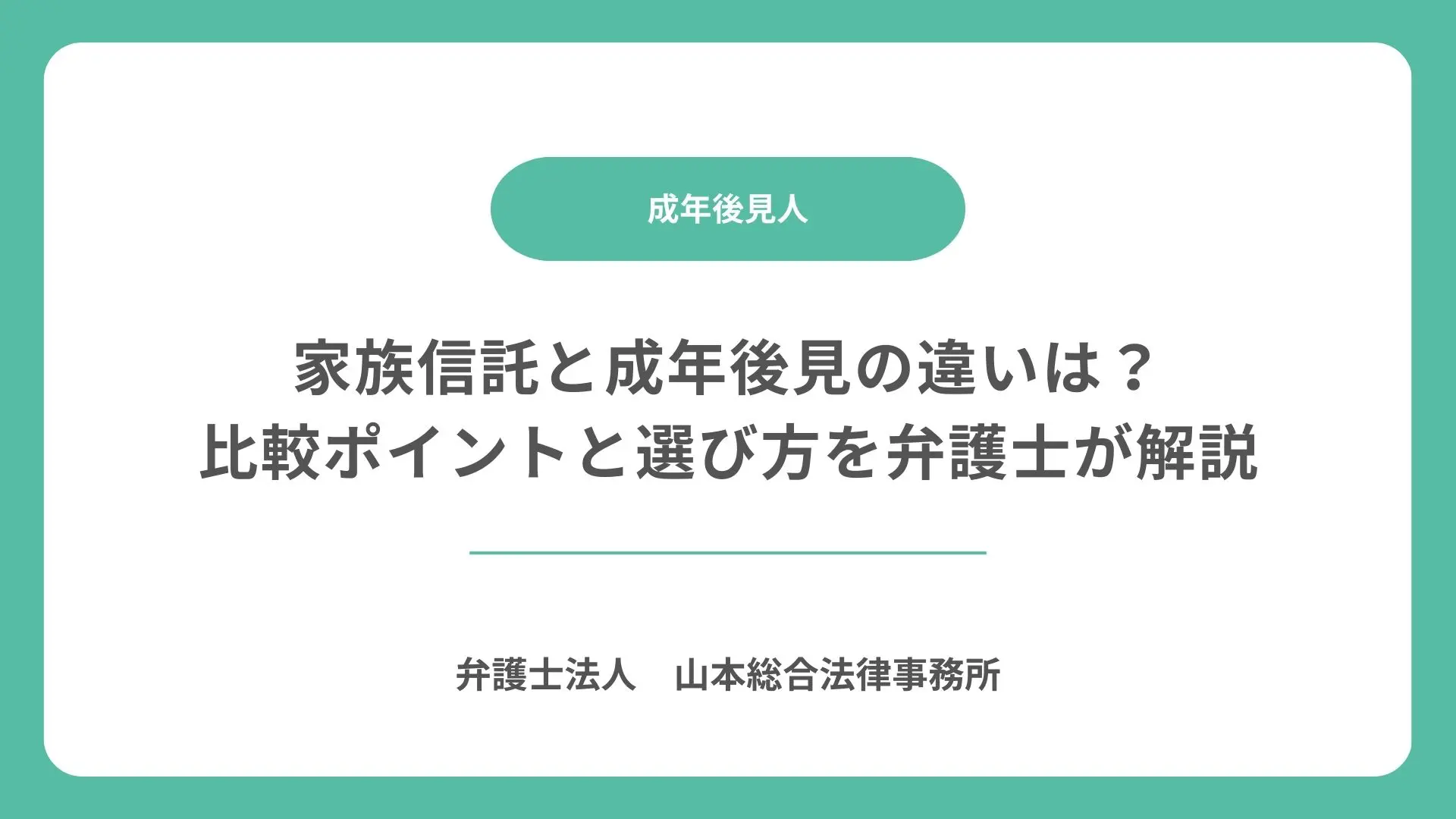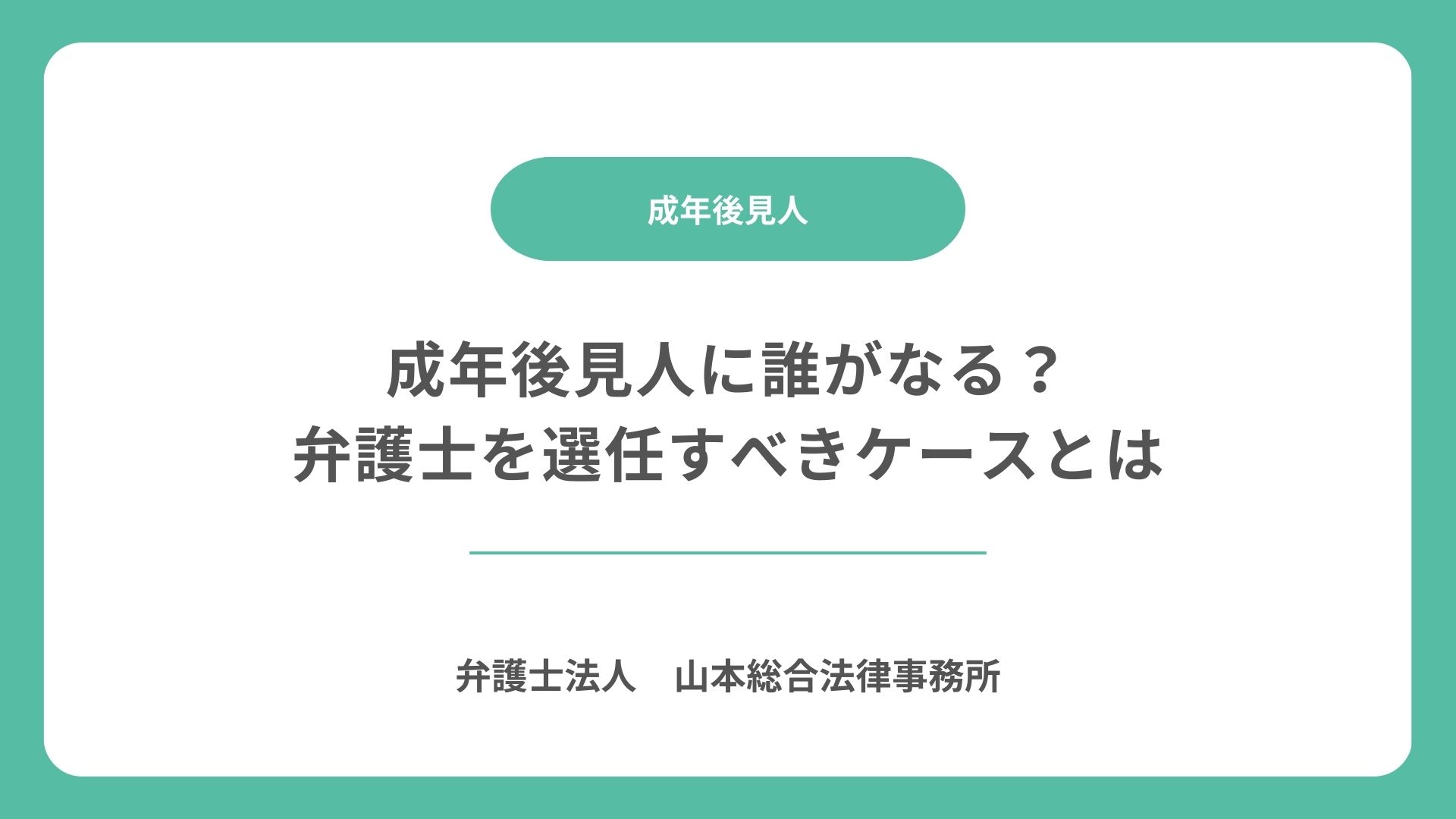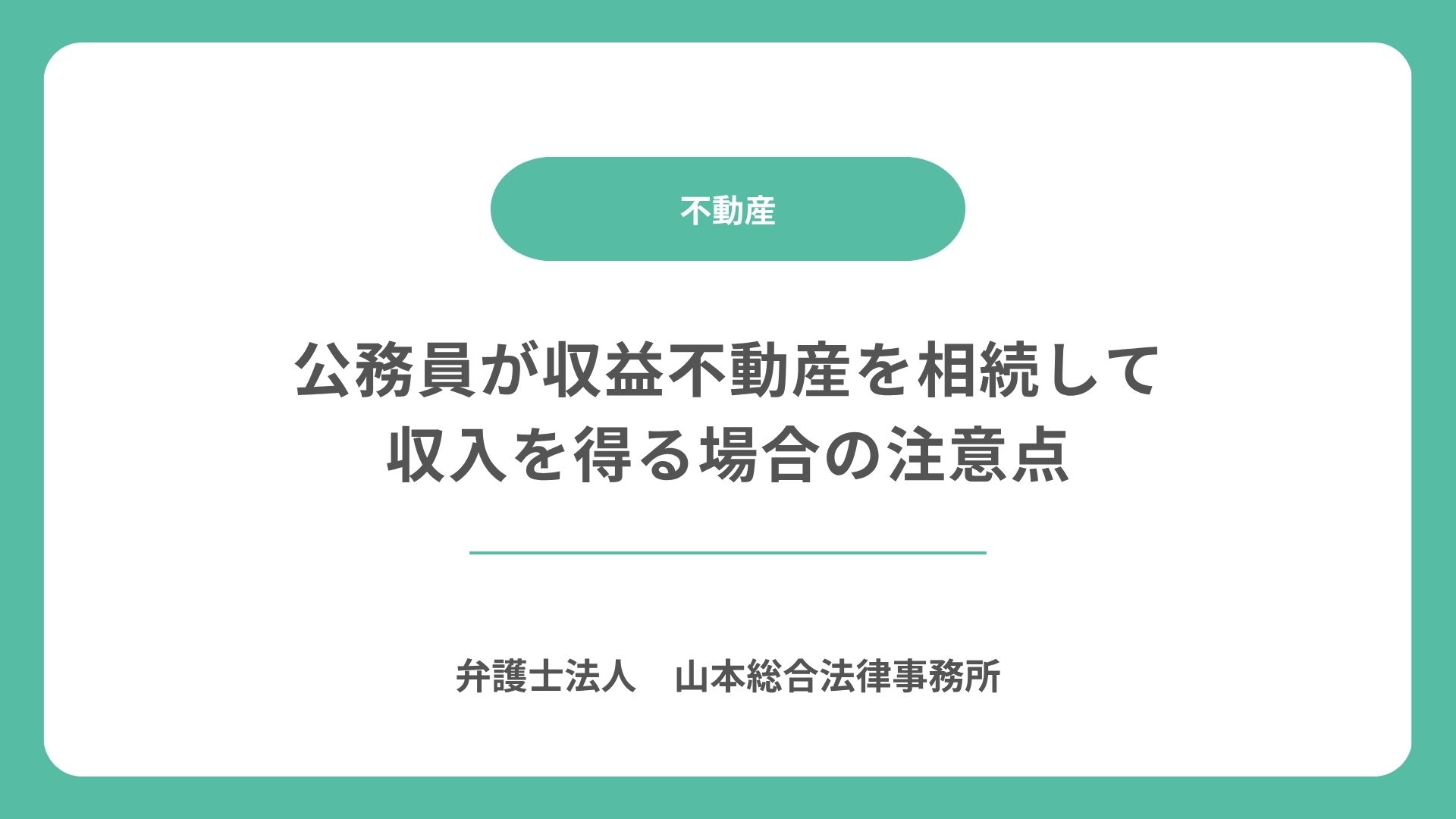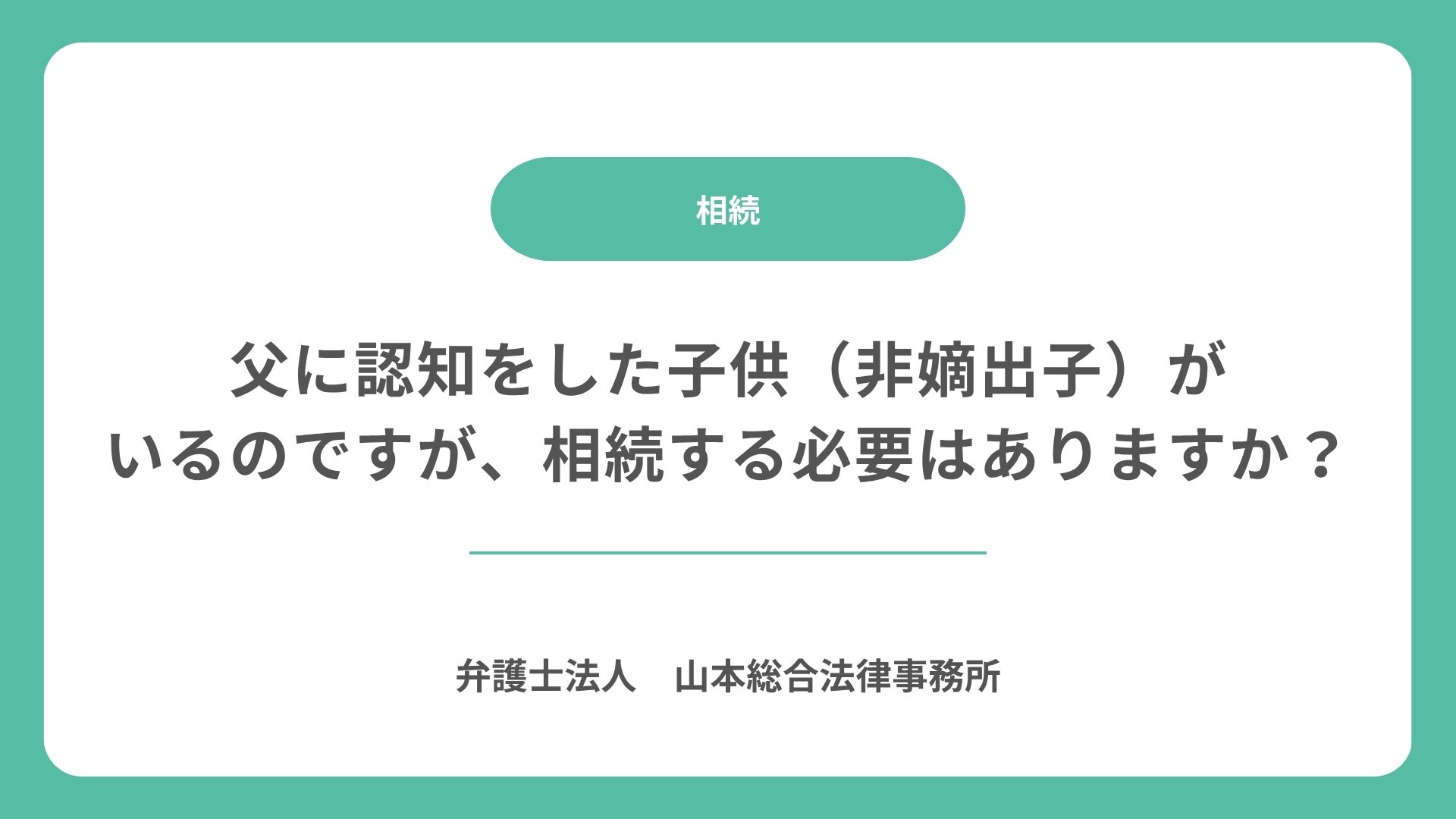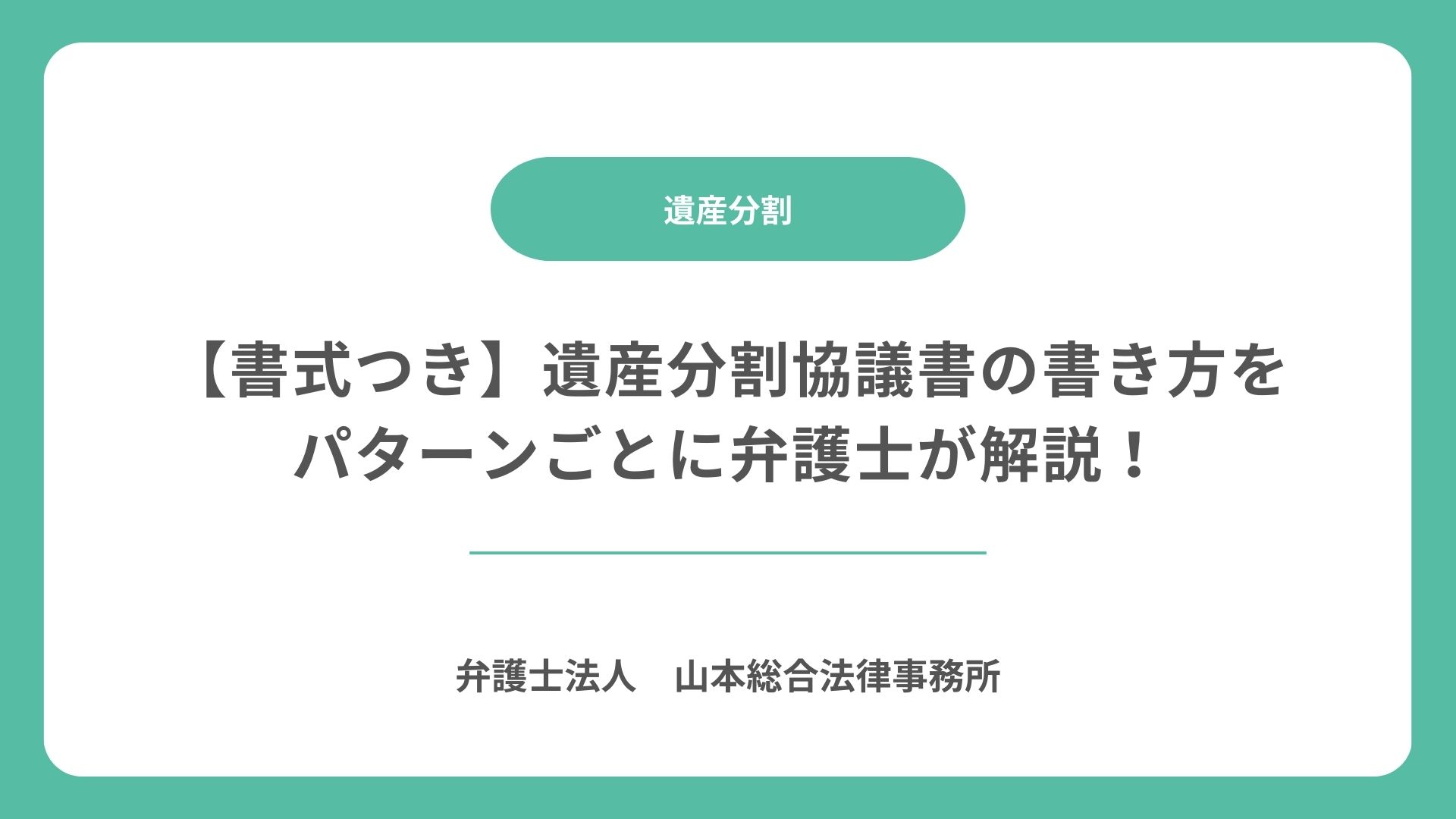- 公開日
- 最終更新日
親の介護をしていたらその努力は認められますか?相続における寄与分とは
- 執筆者弁護士 山本哲也
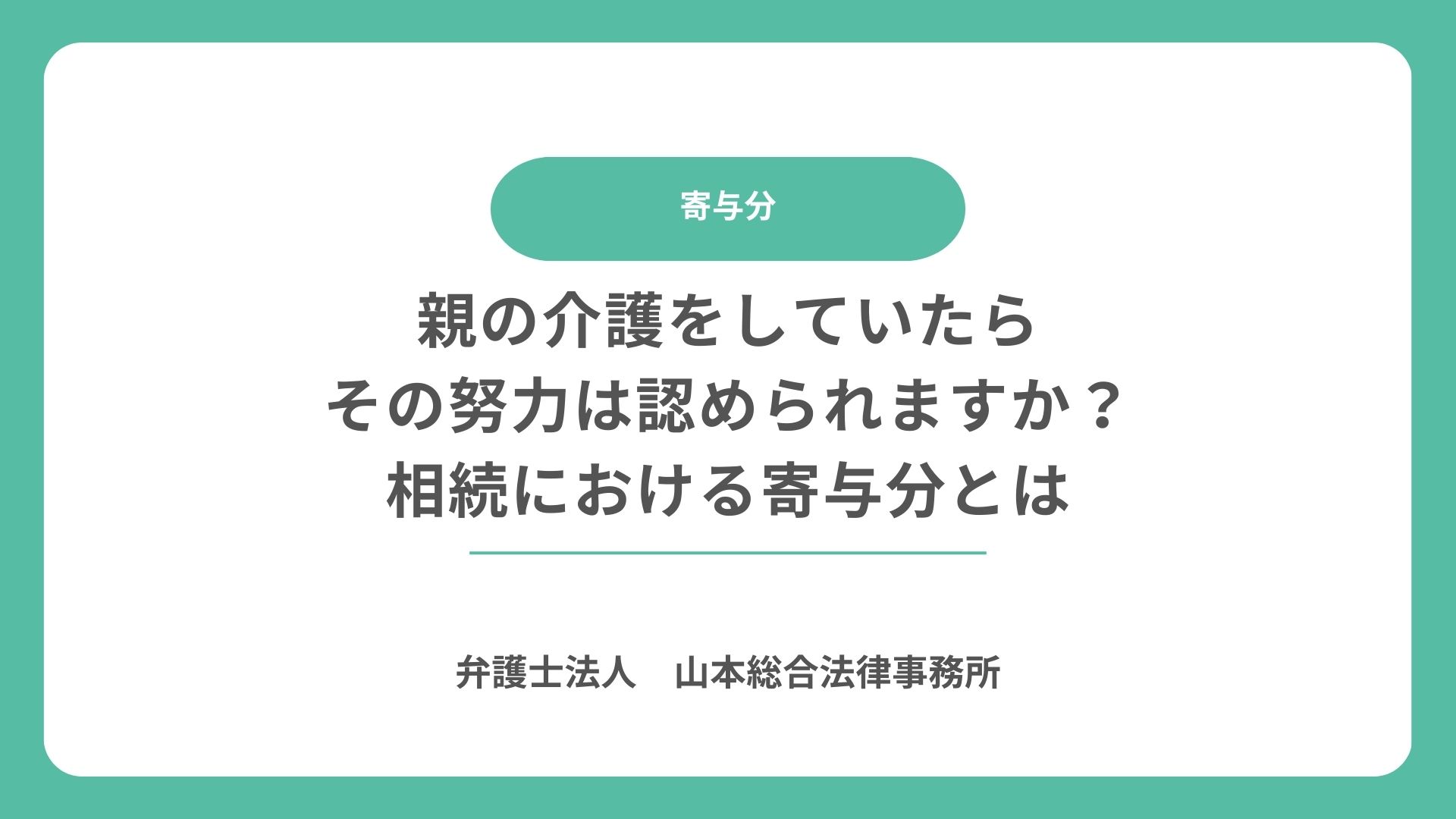
高齢化が進む現代社会では、家族による介護が長期にわたるケースも珍しくありません。特に子どもが親の介護を担ってきた場合、「自分がこれだけ尽くしてきたのだから、その分は相続で考慮してほしい」と思うのは自然な感情です。
相続において、このような貢献を金銭的に評価し、法定相続分に上乗せして受け取る制度が「寄与分」です。そこで、今回は、介護と相続に関わる寄与分の仕組みや実務上のポイントについて解説します。
目次
介護と相続にかかわる寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした人が、その貢献分を相続分に加算してもらえる制度です(民法第904条の2)。
介護の場合、たとえば、長年にわたって親の療養看護を行い、その結果として介護費用や施設費用の支出が抑えられ、親の財産が減らずに済んだというケースで認められます。
具体的に寄与分が認められるケース
寄与分が認められるケース、認められないケースは、以下のとおりです。
長期間の自宅介護
他の兄弟姉妹などがほとんど関与せず、特定の相続人が仕事を調整して自宅で介護した場合、寄与分が認められやすいといえます。
専門性や時間的負担の大きい看護
看護師資格や介護職の経験を生かし、通常なら有償で行われるサービスを無償で提供してきた場合に寄与分が認められることがあります。
被相続人の財産維持への寄与
介護によって施設入所費や外部サービス費用が不要になり、その分財産の減少が免れた場合に、寄与分が認められます。
寄与分が認められない場合
単なる親孝行や短期間の手伝いでは、実務上、「特別の寄与」とまでは評価されません。
寄与分はどのように認めてもらうのか

寄与分は、相続人間の遺産分割協議の際に合意されれば、認められます。
しかし、多くの場合は、相続人のひとりが寄与分を申し出ても、他の相続人から「それは当然の家族の務め」「みんなやっている」と反論され、合意に至らないことも少なくありません。
合意できない場合は、家庭裁判所に「寄与分の額の協議に代わる審判」を申し立てることができます。
この場合、一般的にはまず調停が行われ、調停委員を介した相続人の話し合いで解決できないかが試みられます。調停で解決できない場合に、裁判所が審判を下すこととなります。
裁判所は介護の内容・期間・財産への影響などを総合的に判断し、寄与分の有無とその割合を決めます。
なお、後述するように、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、その手続きの中で、寄与分について主張するという方法もあります。
寄与分を主張するために集めるべき証拠とは?
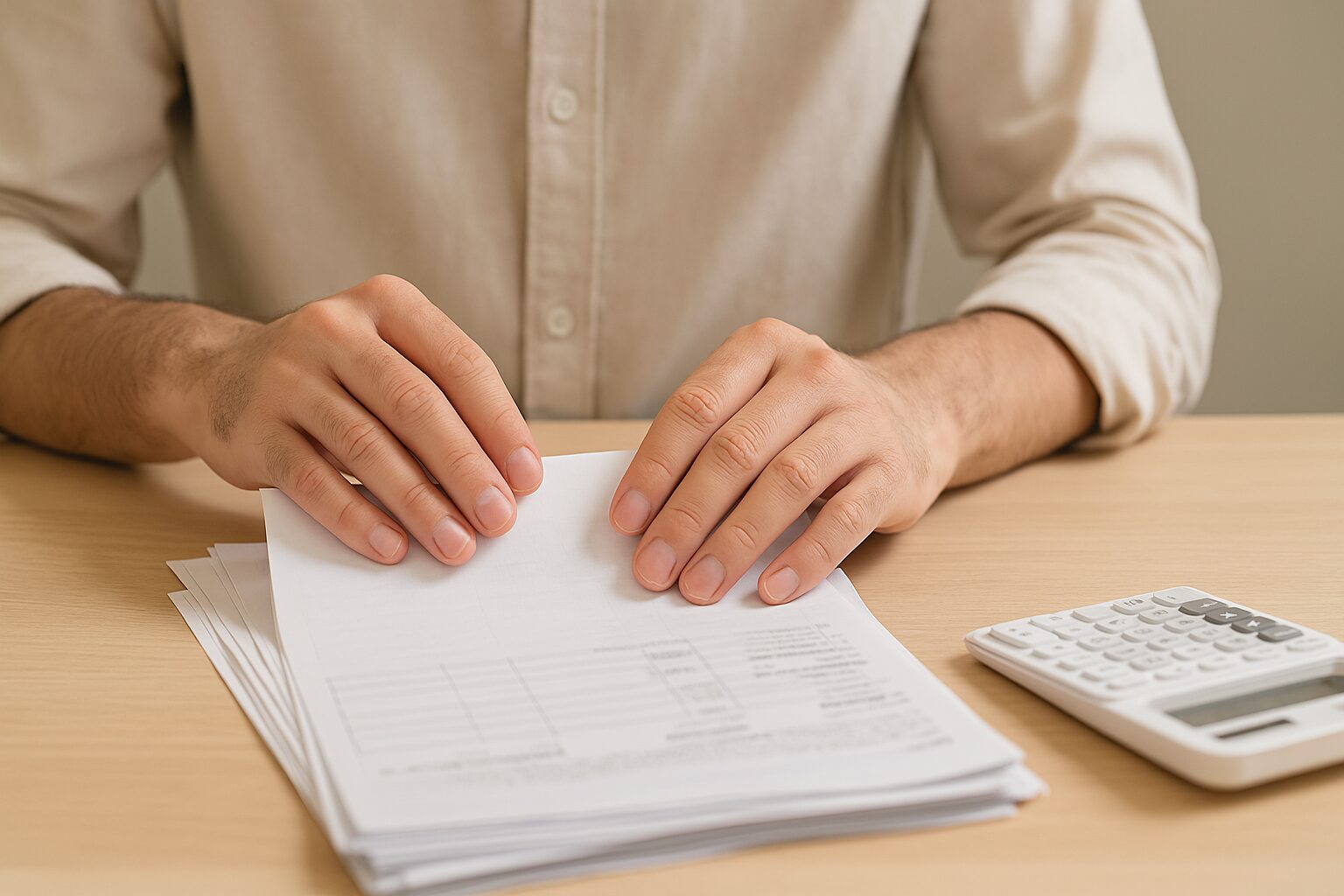
寄与分が認められるかどうかは、被相続人の財産の維持又は増加について「特別の寄与」があったことを立証できるかにかかっています。
そのために有効な証拠の例は次のとおりです。
- 介護記録や日誌(介護の開始日、内容、時間などを記録したメモ)
- 医療機関・介護サービスの利用記録(介護度認定調査票、主治医意見書)
- 介護による支出や負担を示す領収書(交通費、介護用品購入費)
- 勤務時間の変更や離職の記録(介護のために働き方を変えた証拠)
- 第三者の証言(訪問看護師、ケアマネジャー、近隣住民など)
特に、例えば、介護をせずに施設に入れば月にいくらかかったかなど、財産の減少を防いだことがわかる資料があると有効です。
寄与分が認められにくいケース

先にも寄与分が認められないケースについて述べましたが、詳しくは以下のとおりです。
- 短期間の介護(数か月程度)しかしていない場合
- 複数の家族で介護を分担していた場合
- 特別の技能や負担がなく、通常の扶養義務の範囲内とされる介護
- 被相続人の財産維持と明確に結び付かない介護
介護の事実があっても、それが「財産の維持や増加」に直接つながらない場合は、寄与分として認められないことがあります。
寄与分が認められると、どのくらい遺産がもらえる?
寄与分は、遺産の総額に上乗せする形で計算されます。
例えば、遺産総額が3000万円、相続人が長男・次男の2人、長男の寄与分が500万円と認定された場合には、以下のように計算します。
まず、遺産総額を修正して、3000万円+500万円で3500万円とします。
これを、法定相続分(1/2ずつ)に基づいて、長男、次男とも3500万円 × 1/2 の1750万円と計算します。
しかし、実際には、遺産は3000万円しかないので、長男が500万円多くもらえるように次男の分を減額し、最終的な相続分は、長男は1750万円、次男は1750万円-500万円で1250万円となります。
話し合いで認めてもらえない場合の対処法

相続人間の話し合いで寄与分を認めてもらえない場合には、遺産分割調停を起こし、その際に寄与分を主張するか、「寄与分の額の協議に代わる審判」を申し立てることとなります。
調停や審判の手続においては、証拠を整理して主張を明確に行うことが必要です。
証拠として介護サービスを利用した場合の費用見積もりや市場価格を提示することによって、寄与分額の根拠を補強して主張することが可能となります。
まずは弁護士にご相談ください

寄与分は、証拠の有無や主張の仕方で結果が大きく変わるものです。
介護の実態を適正に評価して主張するには、実務経験のある弁護士のサポートが有効です。
弁護士は、事実関係を整理して、必要な証拠を収集するよう指示し、適切に金額の評価をすることができます。また、これらの結果をもとに調停・審判で代理人として活動することが可能です。
「介護をした分、少しでも報われたい」と感じている方は、早めに弁護士に相談することで、証拠の散逸を防ぎ、有利な交渉が可能になります。
弁護士法人山本総合法律事務所は、寄与分の問題について精通しております。相続に当たって寄与分の主張をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。