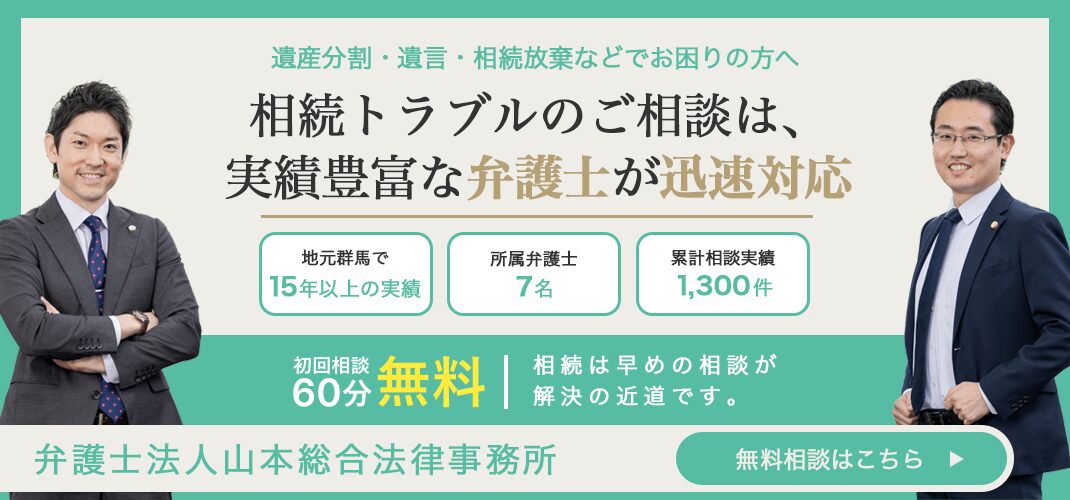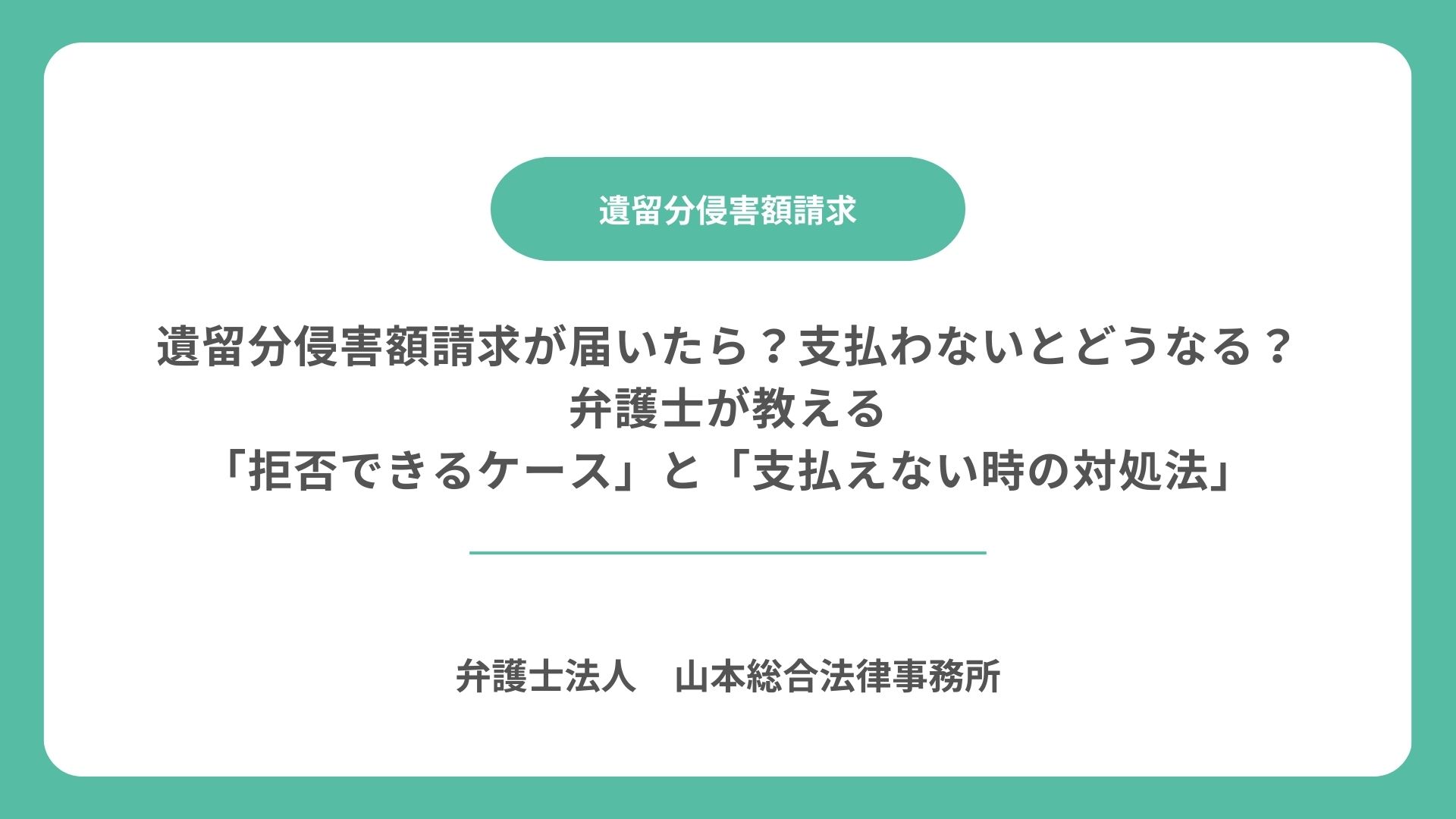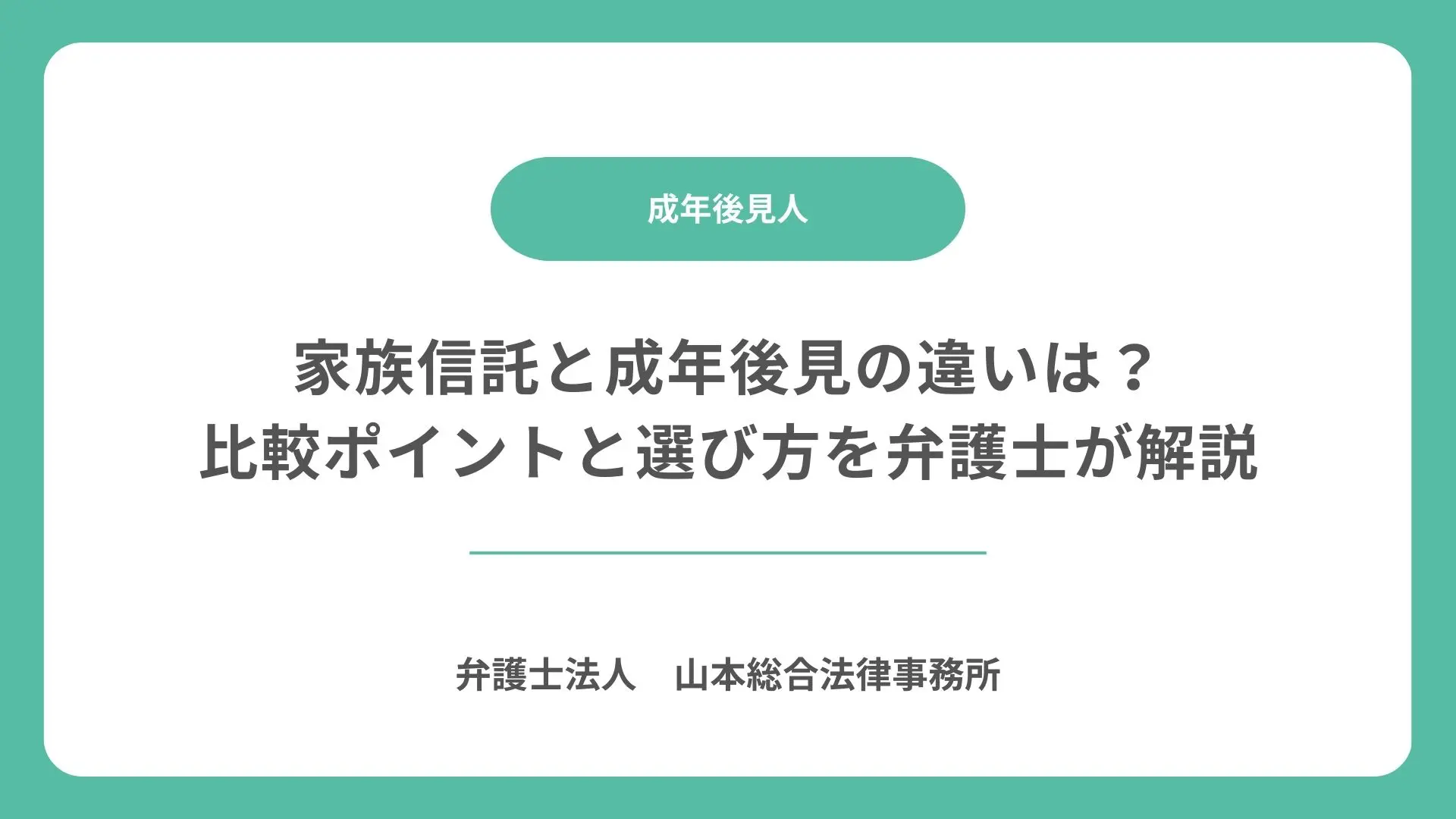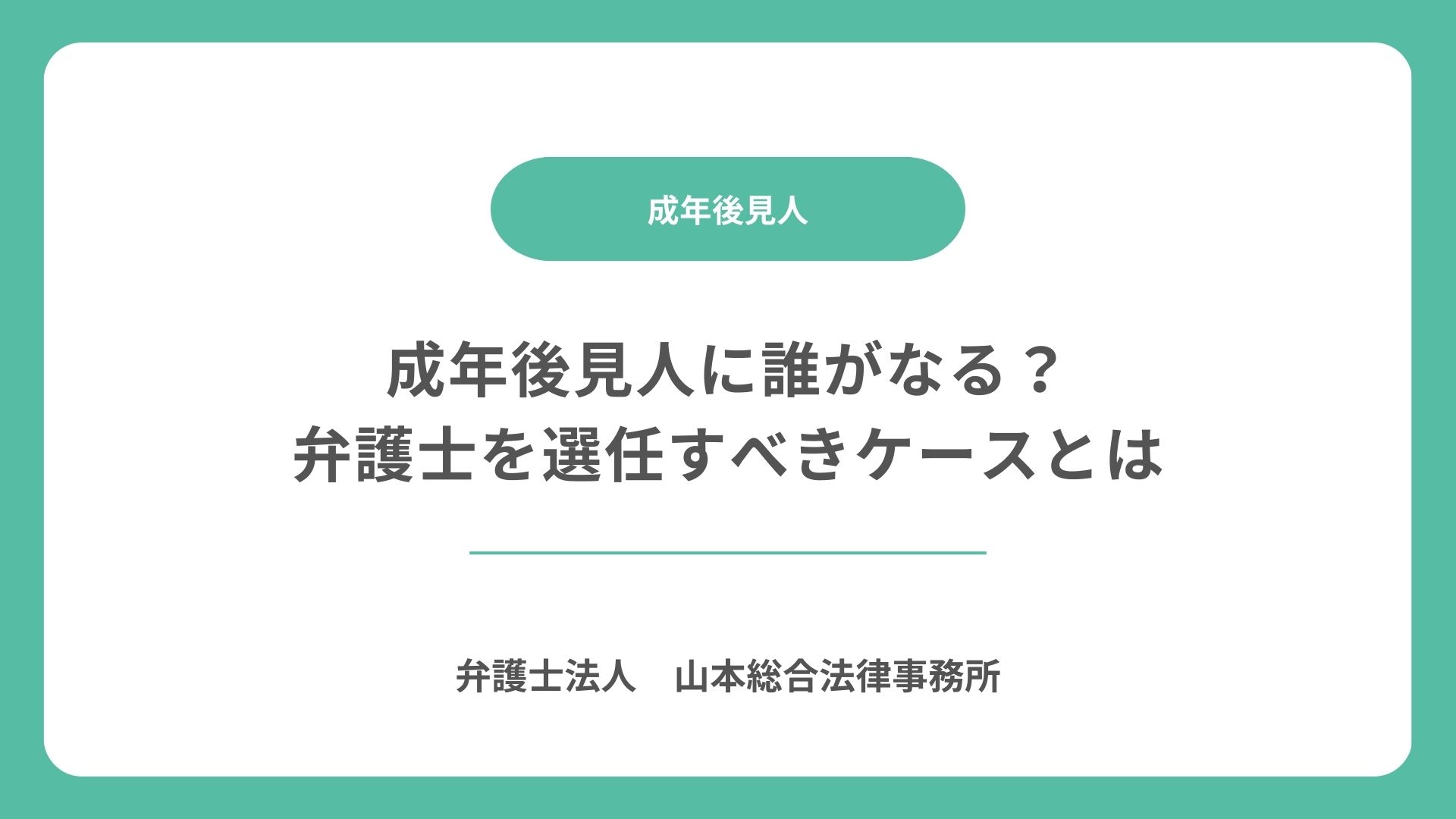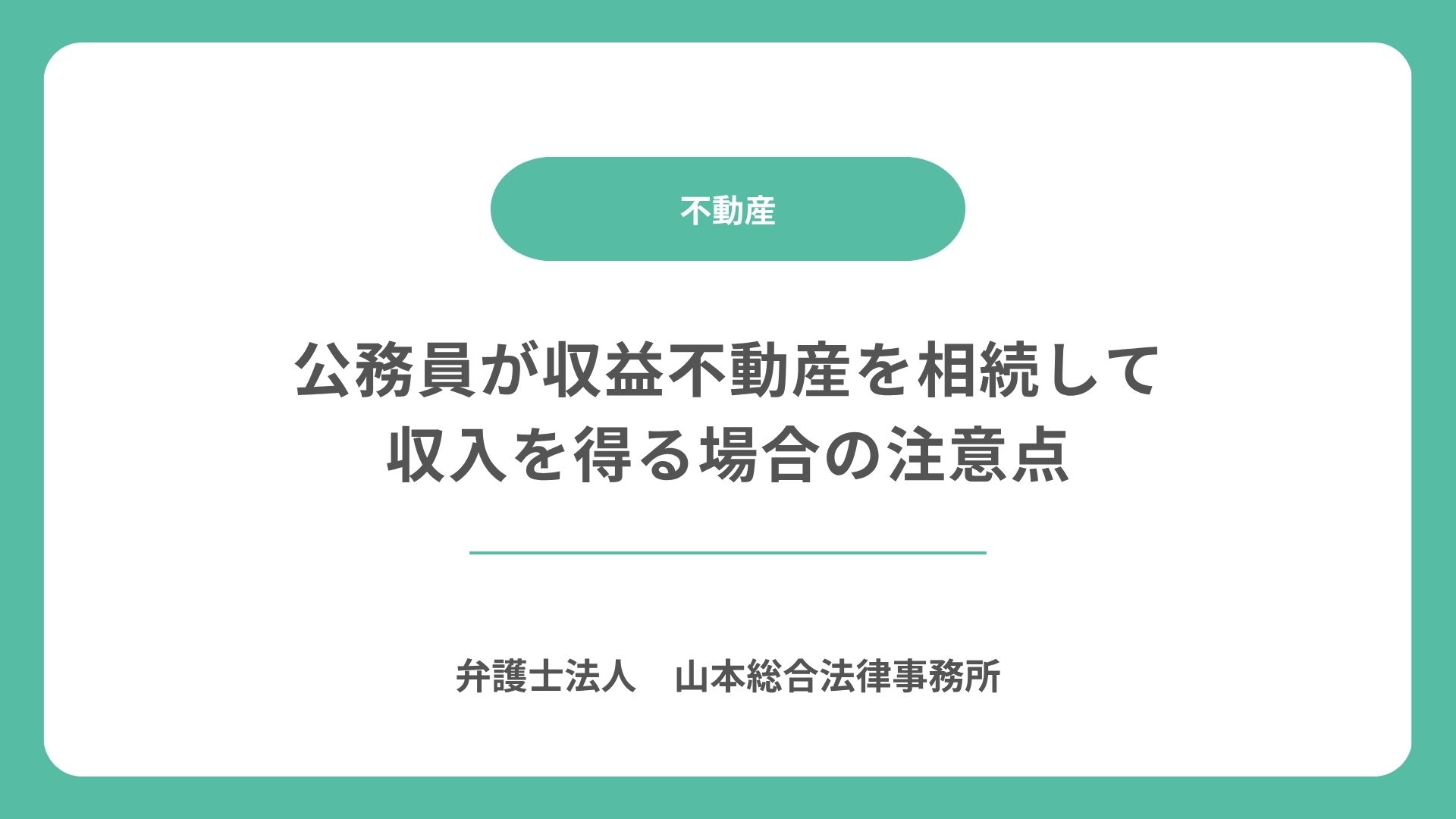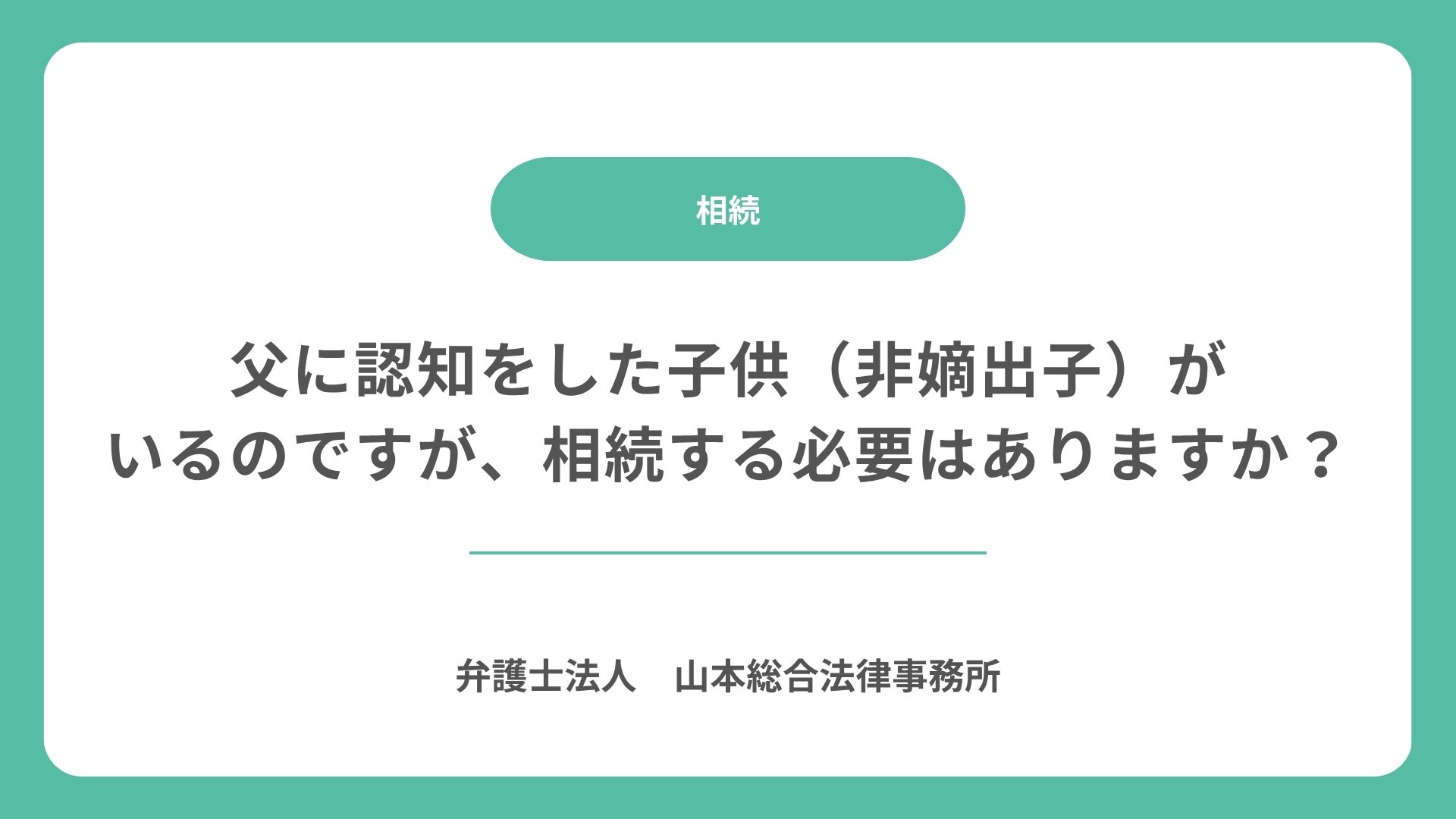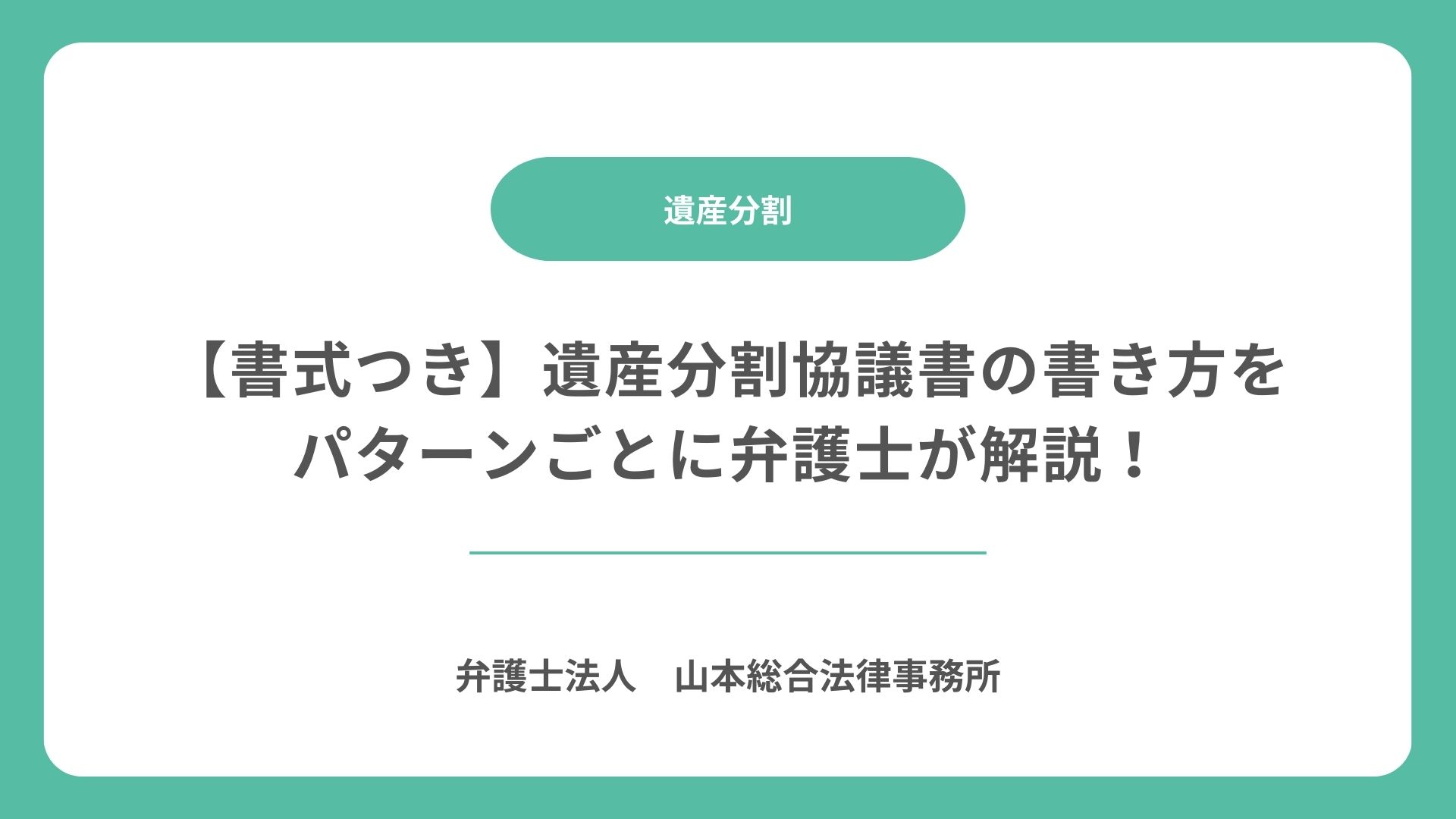- 公開日
- 最終更新日
相続人が多く、収拾がつかない!相続人が多すぎる場合の遺産分割
- 執筆者弁護士 山本哲也
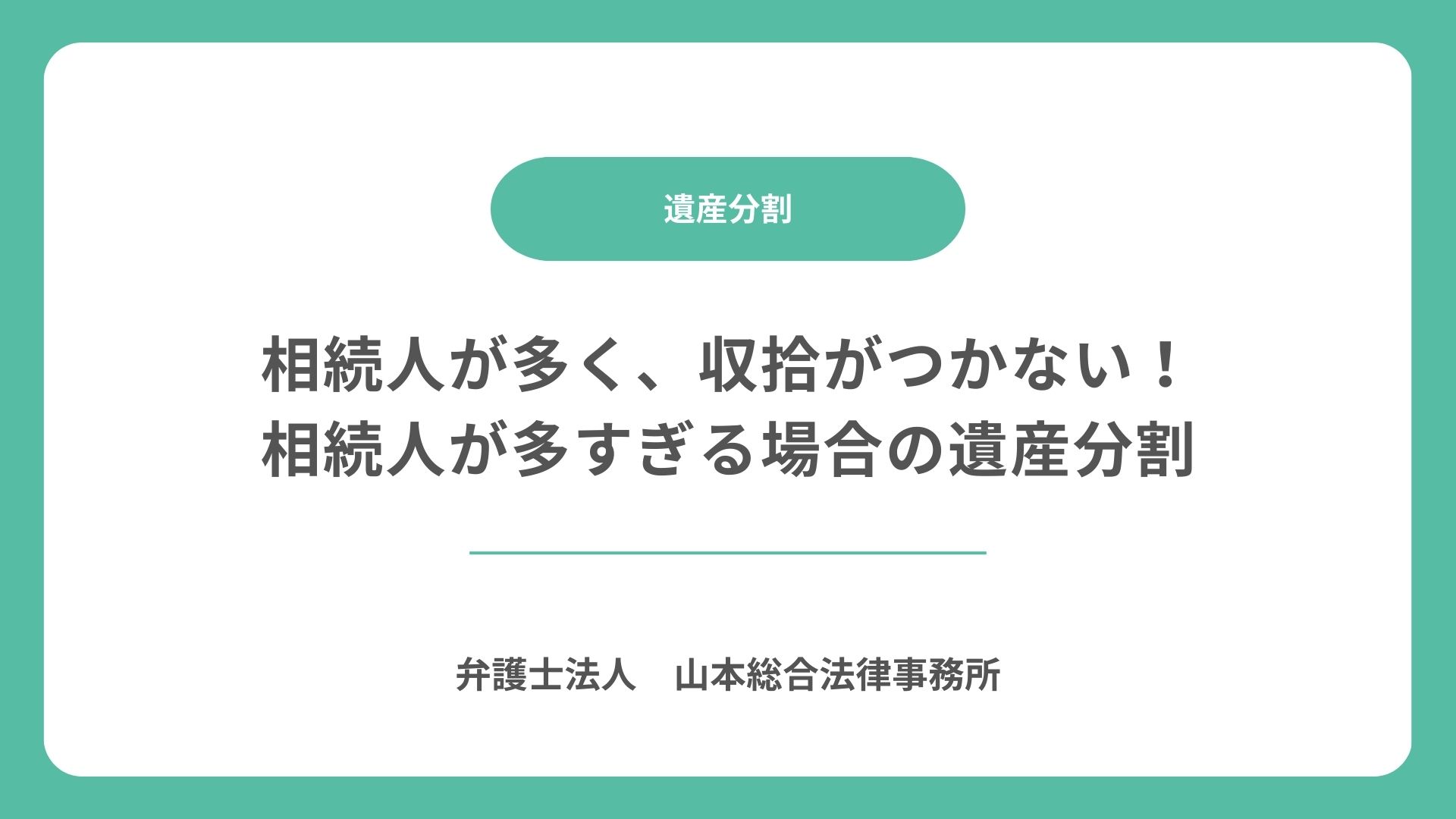
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産を、誰がどのように分けるのかを決める遺産分割協議が必要になります。
相続人が2~3人程度であれば、話し合いも比較的スムーズに進むことが多いのですが、相続人が10人以上に及ぶケースでは、一筋縄ではいかなくなるのが実情です。
そこで今回は、相続人が多い場合に生じやすいトラブルと、その対応策について解説します。
目次
相続人が多い場合によくあるトラブル

相続人が多い場合に起こりがちなトラブルにはどのようなものがあるでしょうか。
話し合いをするために集まることができない
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、合意することが必要です。
しかし、相続人が多ければ多いほど、日程調整だけで大きな負担となります。
特に遠方に住んでいる人が多い場合、実際に集まること自体が困難です。
そのため、書面でのやり取りや代理人を立てて進めることが多くなりますが、それでも全員の意思を一致させるのは容易ではありません。
面識のない相続人がいる
被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合、これまで一度も顔を合わせたことがない相続人が存在するケースもあります。
面識がないと信頼関係がなく、相続財産の分け方について意見が対立しやすくなります。
また、そもそも自分が相続人であることの自覚がなく、取り合ってくれない場合もあります。
連絡の取れない相続人がいる
音信不通の相続人がいると、遺産分割協議を進めることができません。
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要であるため、連絡がつかない一人がいるだけで、協議は成立しなくなります。
このような場合、家庭裁判所の調停や不在者財産管理人の選任手続を利用する必要が出てきます。
相続人が認知症になっている
相続人の中に認知症の人がいると、そのままでは遺産分割協議に参加できません。
この場合は家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
後見人が選任されるまで時間がかかるため、遺産分割の手続全体が長期化する要因となります。
未成年の相続人がいる
未成年の相続人は、単独で法律行為を行うことができません。
親権者が代理人となりますが、その親権者も相続人である場合は「利益相反」となり、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことが必要になります。
このように、未成年者が含まれると、裁判所の関与が必要になることが少なくない点に注意が必要です。
相続人が多くなる可能性がある、注意すべき状態

相続人が多くなりやすいのは以下のような状態のときです。
被相続人に子がいない
子どもがいない夫婦の一方が亡くなると、配偶者に加えて、亡くなった人の両親あるいは兄弟姉妹が相続人となります。
さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子ども(甥姪)が代襲相続するため、一気に相続人の数が増えてしまいます。
数次相続が発生している
被相続人が亡くなった後、遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなると、さらにその相続人の相続が発生します。
これを「数次相続」といいます。
数次相続が起きると、相続人が雪だるま式に増え、誰がどの割合で相続するのか複雑になっていきます。
相続人が多い場合の遺産分割の進め方

以下では、相続人が多い場合に、どのような段取りで遺産分割を進めるべきかについて解説します。
相続人の調査
まずは「誰が相続人なのか」を正確に確定させることが最優先になります。
戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取り寄せ、相続関係説明図を作成します。
相続人が多い場合、調査漏れがあると、やり直す必要が生じ、手続全体が遅延してしまいます。
遺産分割協議の実施
相続人全員が確定したら、遺産の内容を明らかにし、分割方法について協議します。
相続人が多数の場合は、一人が代表者となり、取りまとめ役を担うこともあります。
協議がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印します。
相続人全員の署名押印がそろわなければ、遺産分割協議が成立したものとは認められないので、注意が必要です。
遺産分割調停の申し立て
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停委員が間に入り、公平な立場で話し合いを進めてくれるため、合意に至りやすくなります。
調停でもまとまらなければ、最終的には裁判所の審判によって分割方法が決められます。
相続人が全員集まらずに遺産分割を行うと?

相続人全員の同意がないまま遺産を分けてしまうと、その遺産分割は効力が認められません。
たとえ大多数が合意していても、一人でも欠ければ、法的効力は認められないのです。
そのため、後から「自分は同意していない」と主張されると、改めて遺産分割をやり直さなければならず、大きなトラブルにつながります。
相続人が多い場合、調整役を務める相続人には大きな負担がかかります。
戸籍の調査、相続人全員との連絡、協議の取りまとめ、書類の整備など、専門的な知識と労力が必要です。
さらに認知症や未成年者が絡むと、家庭裁判所での手続も不可欠です。
このような場合は、早めに弁護士に相談することが有効です。
弁護士が相続人全員への連絡や調整、調停や審判の申立てを代理することで、スムーズに手続を進めることが可能になります。
相続人が多い相続ほど、専門家のサポートが大きな助けとなるのです。
相続人が多いと、遺産分割は複雑化し、トラブルが起こりやすくなります。
全員の同意が必要であることから、わずかな行き違いでも協議が進まなくなるのが実情です。
弁護士法人山本総合法律事務所は、相続人多数の遺産分割の実績があり、このような事案でお困りの方のサポートが可能です。
相続人が多くて手続がなかなか進まないとお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。