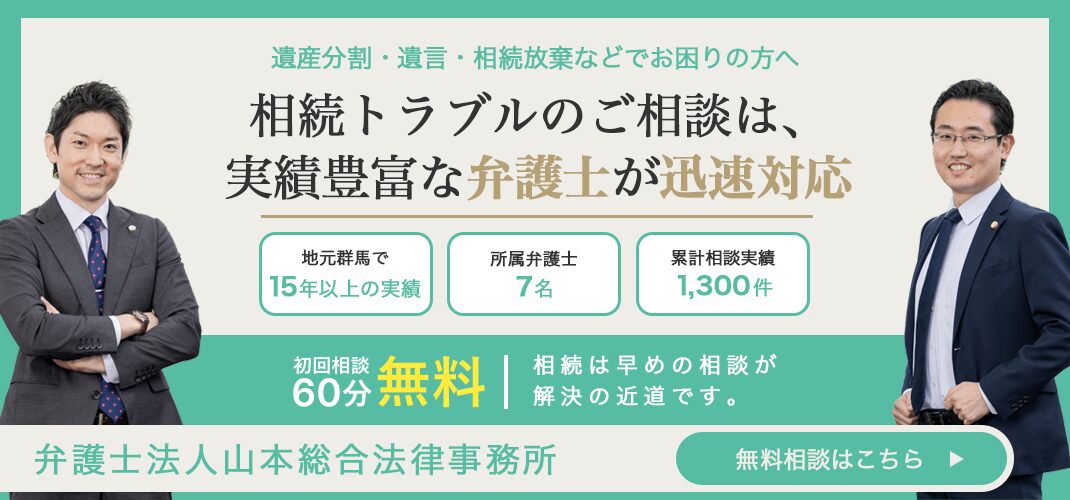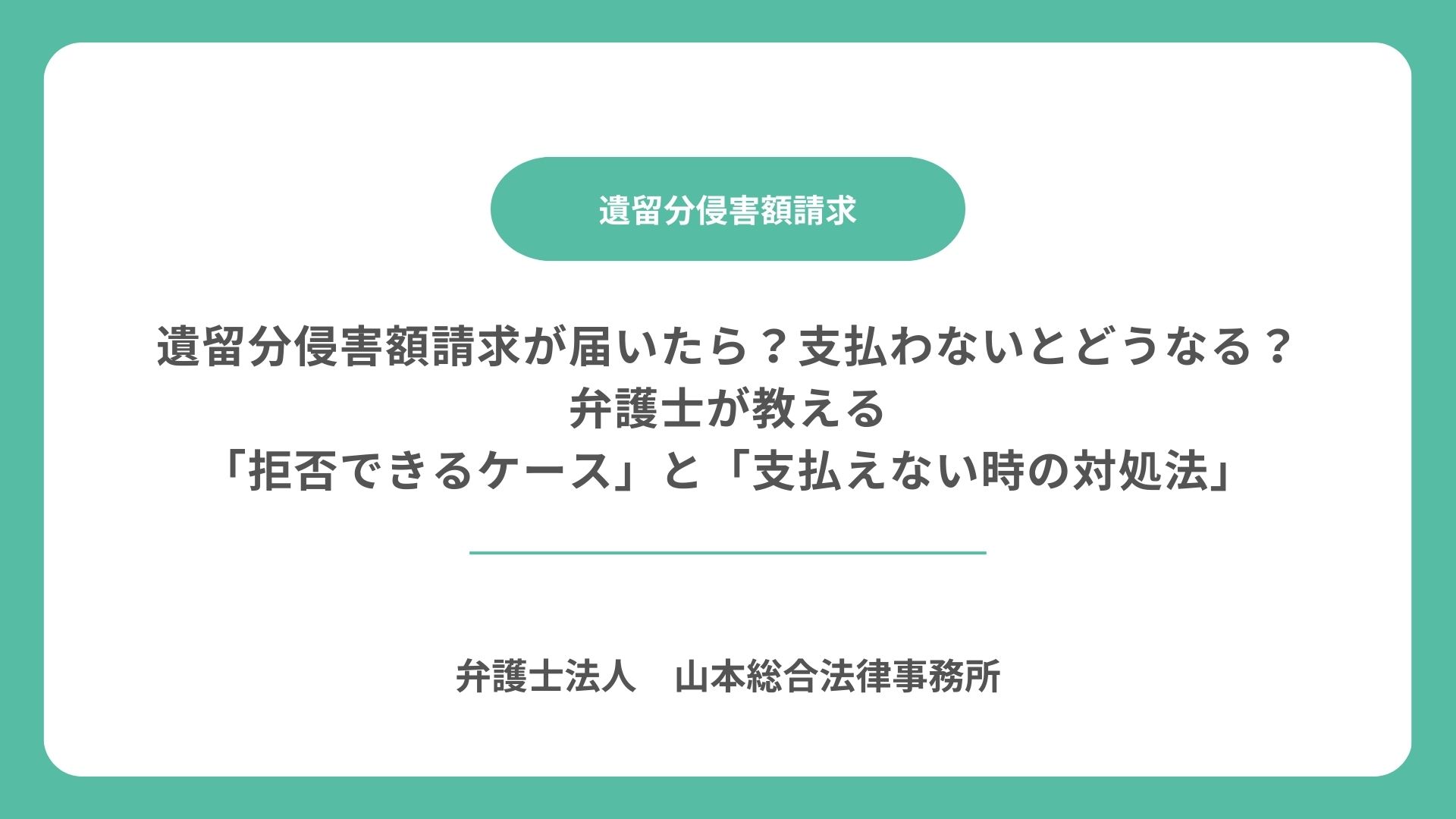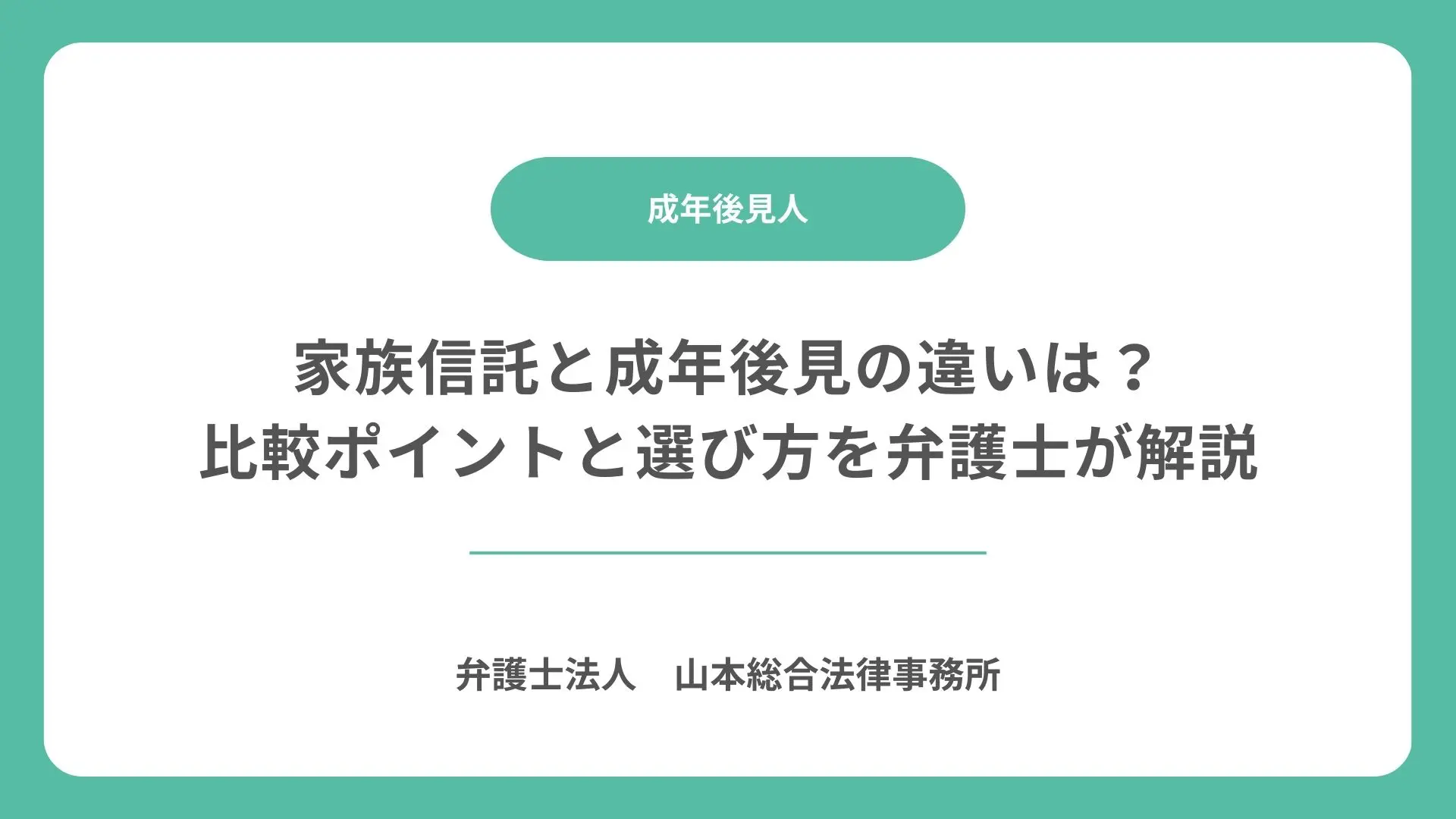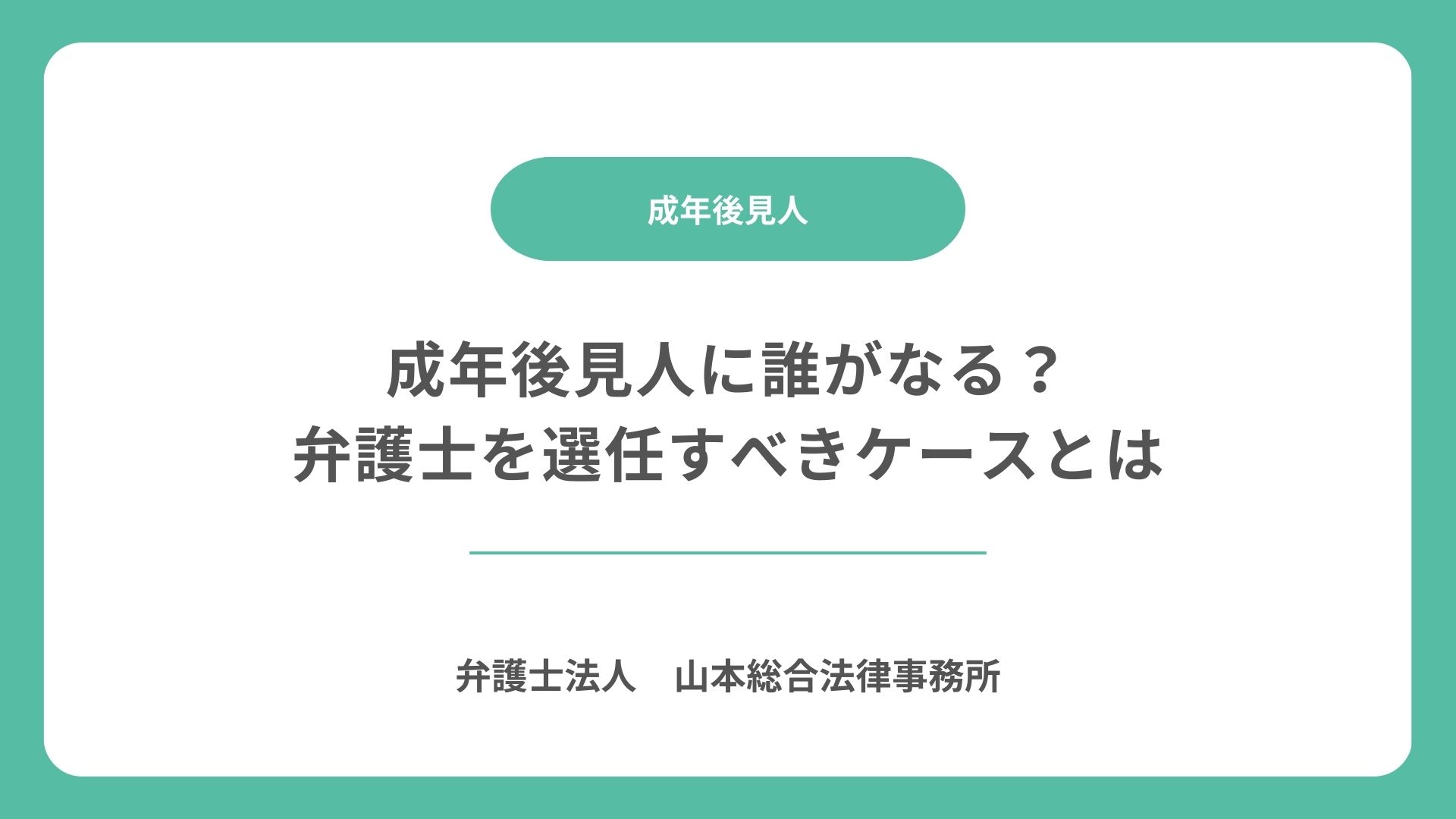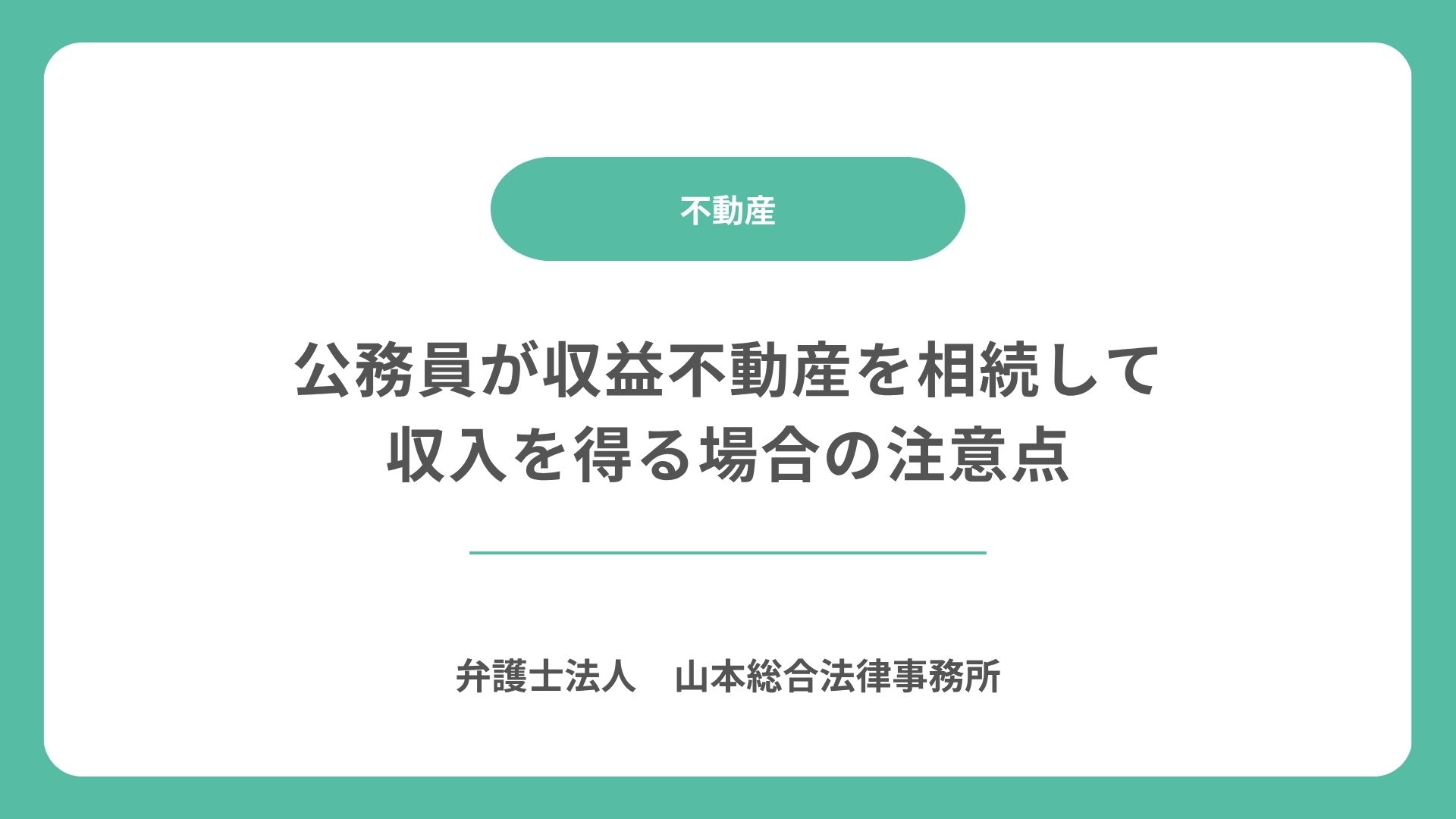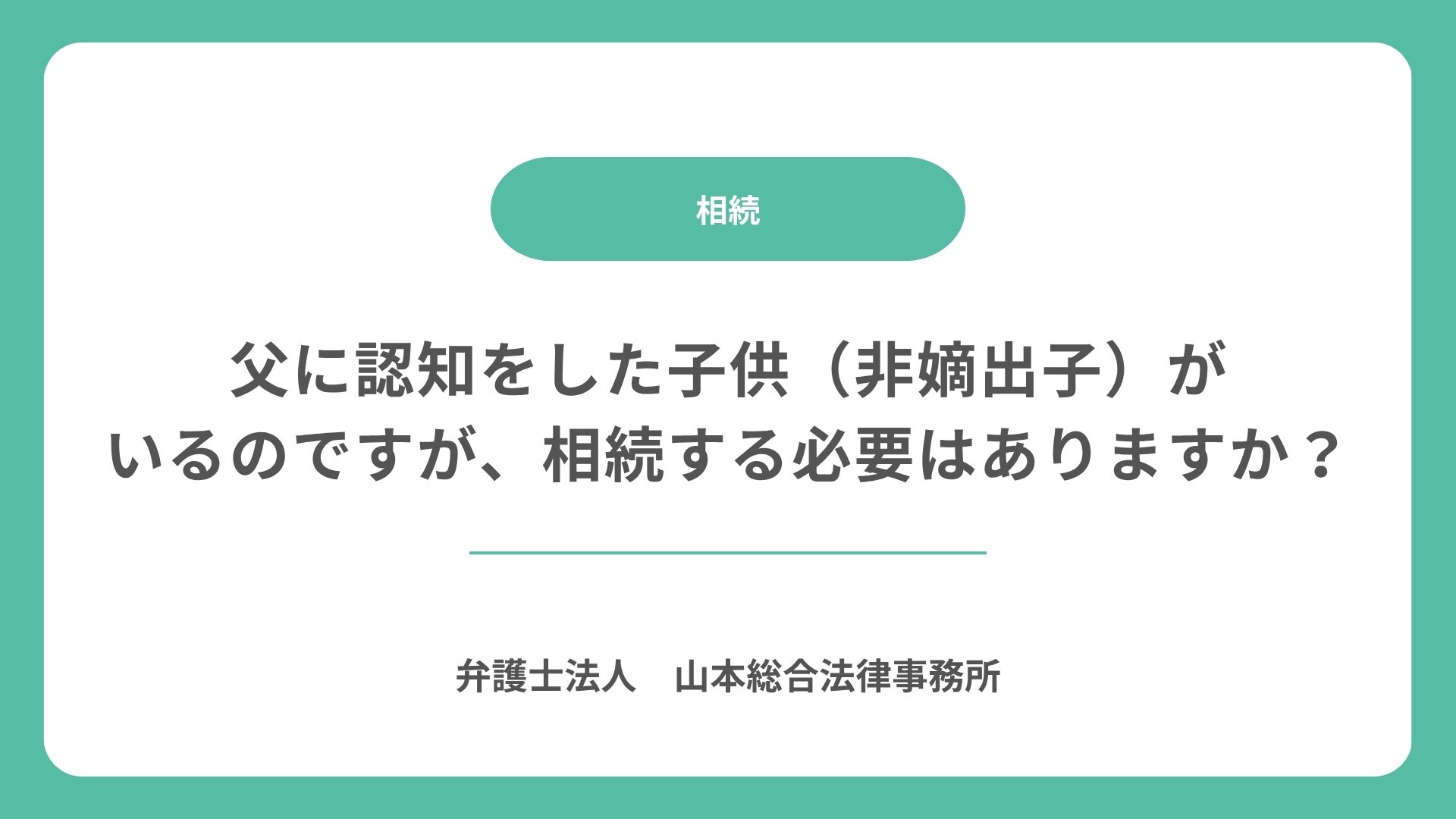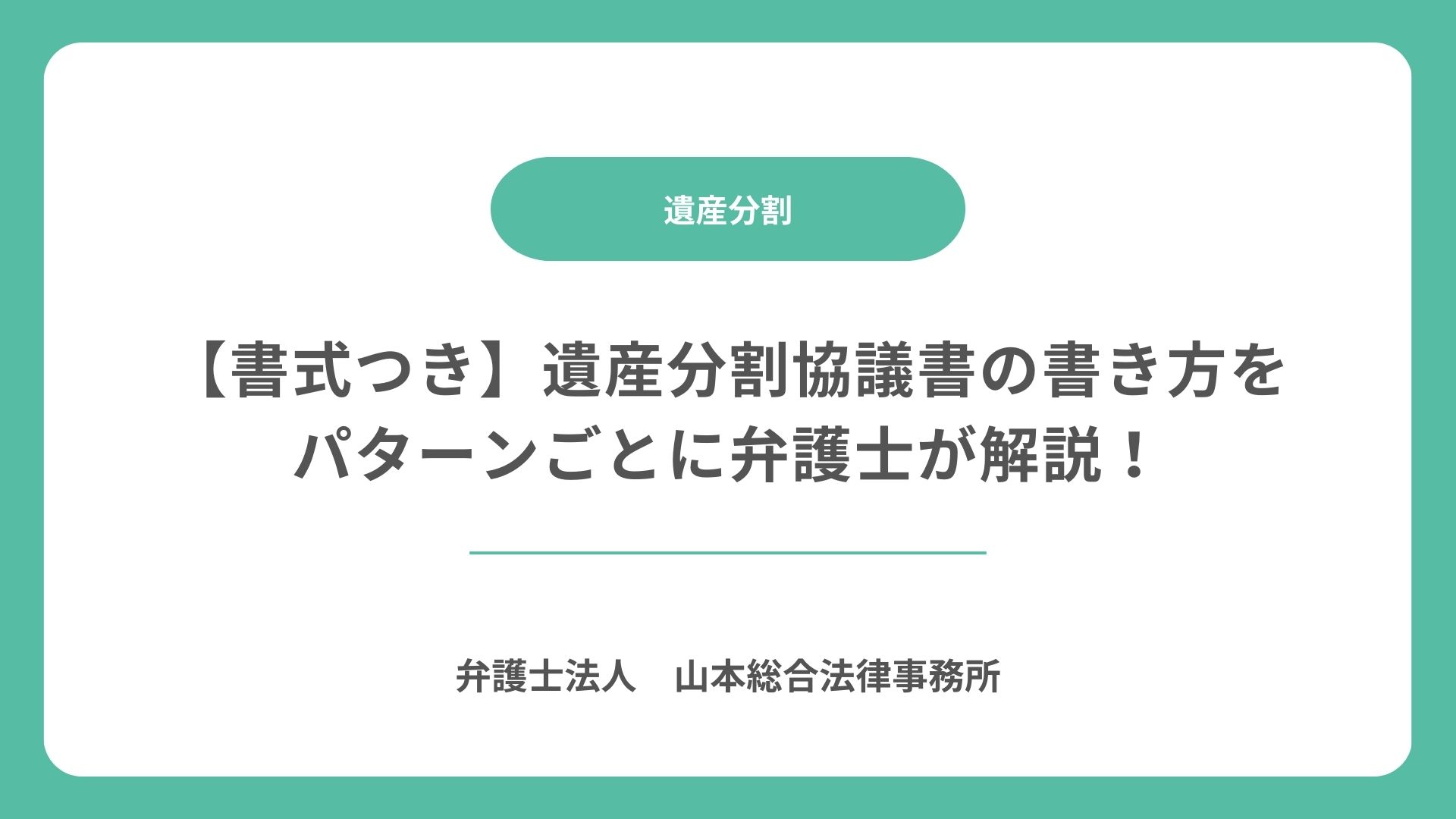- 公開日
- 最終更新日
内縁の妻に財産を残したい!相続権は無いが、遺贈や生前贈与で実現できる?
- 執筆者弁護士 山本哲也
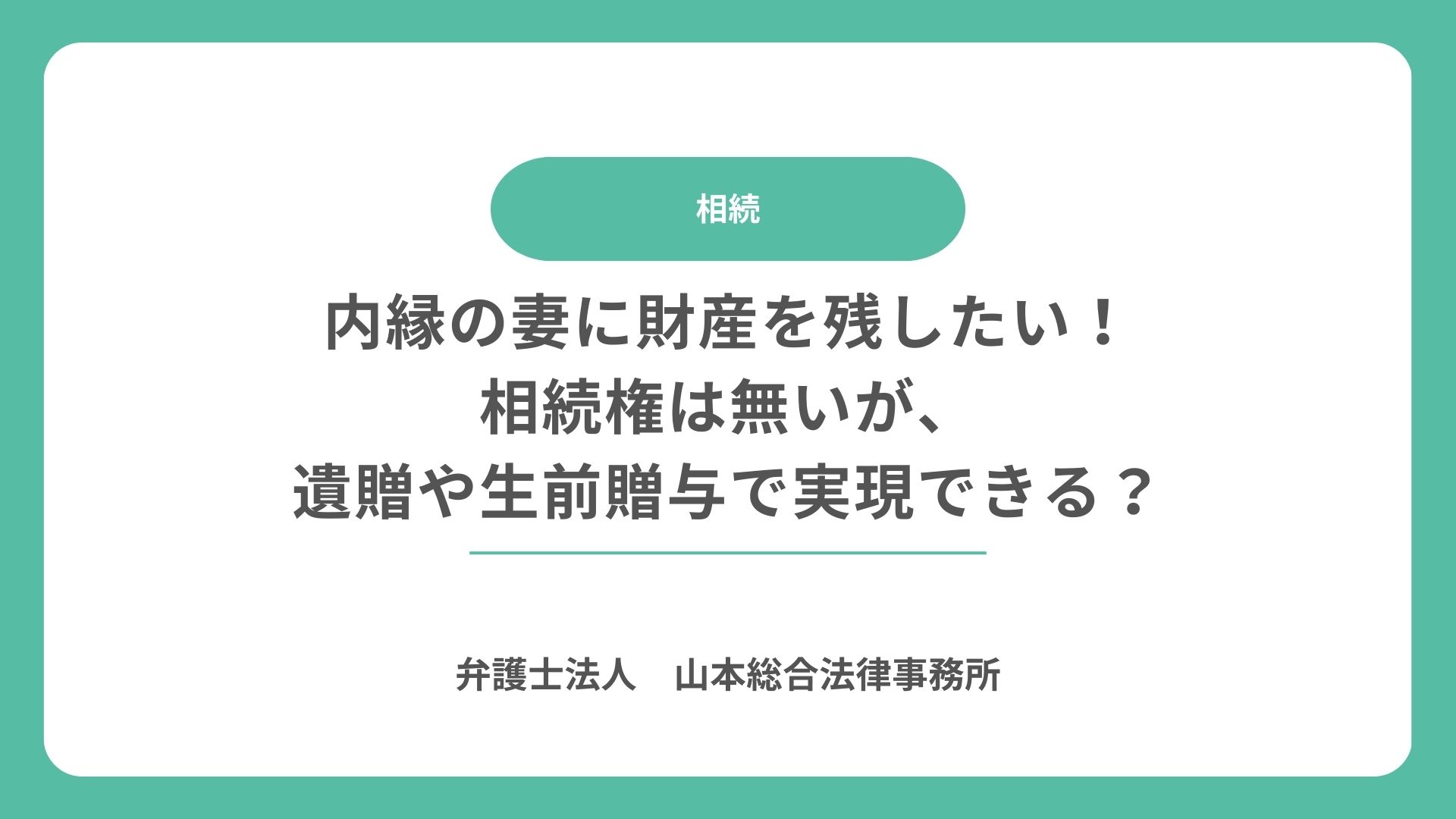
近年、婚姻届を出さずに事実婚の形を選ぶカップルが増えています。
法律上は婚姻関係にないものの、夫婦同様に生活を共にし、長年支え合ってきた「内縁の妻」に財産を残したいと考える方は少なくありません。
しかし、現行法では、内縁の妻には法定相続権が認められていません。
そのため、何の対策もせずに亡くなった場合、内縁の妻には何の財産も残せないリスクがあります。
そこで、今回は、「なぜ内縁の妻には相続権がないのか」という問題から、遺言や生前贈与といった生前対策、さらに実務で起こりやすいトラブルを整理し、「想いを形にする方法」について解説していきます。
目次
内縁の妻になぜ相続できない?「法定相続人」の厳格なルール
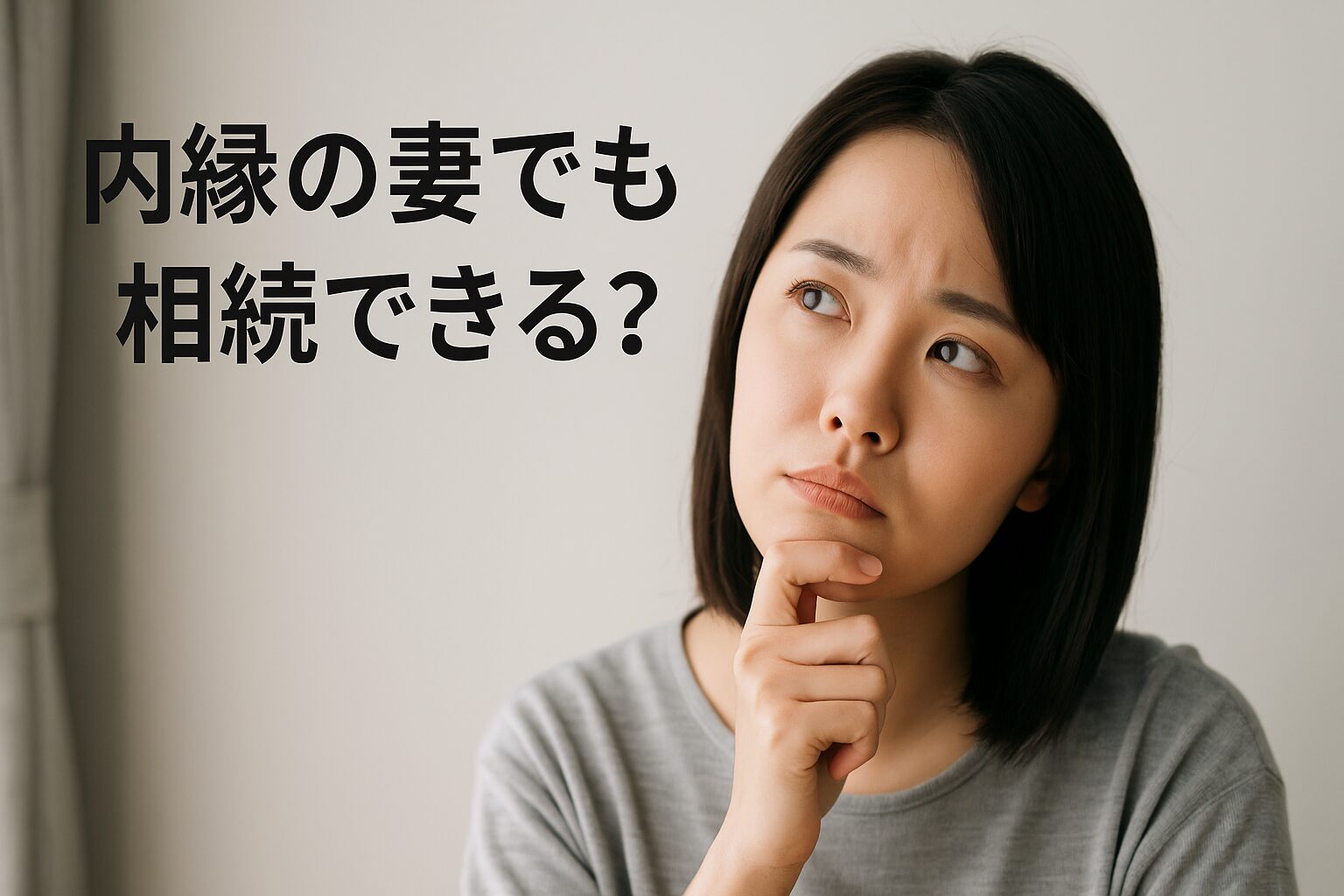
最初に、内縁の妻はなぜ相続できないのかについて解説します。
民法が定める「法定相続人」とは
相続において、誰がどの範囲で財産を受け取る権利を持つかは、民法で厳格に定められています。
法律で相続ができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。
具体的には、配偶者(婚姻届を出した配偶者を指します。)は常に相続人となり、そのほかに子ども、直系尊属(親・祖父母など)、兄弟姉妹が順位に応じて加わります。
ここで重要なのは、「内縁の妻」は法律上の「配偶者」には含まれないという点です。
たとえ数十年同居し、実際には法律上の夫婦と同じ生活をしていたとしても、相続権が認められません。
何もしなかった場合、財産は国庫へ
法定相続人が一切存在せず、遺言も残されていない場合、財産は最終的に国庫へ帰属します。
つまり、長年生活を共にしてきた内縁の妻であっても、対策を取らなければ特別に例外的な場合を除いて一切財産を受け取ることができないということです。
「当然もらえるだろう」という思い込みは危険であり、あらかじめ適切な法的手段を講じておくことが不可欠です。
想いを形にするための生前対策
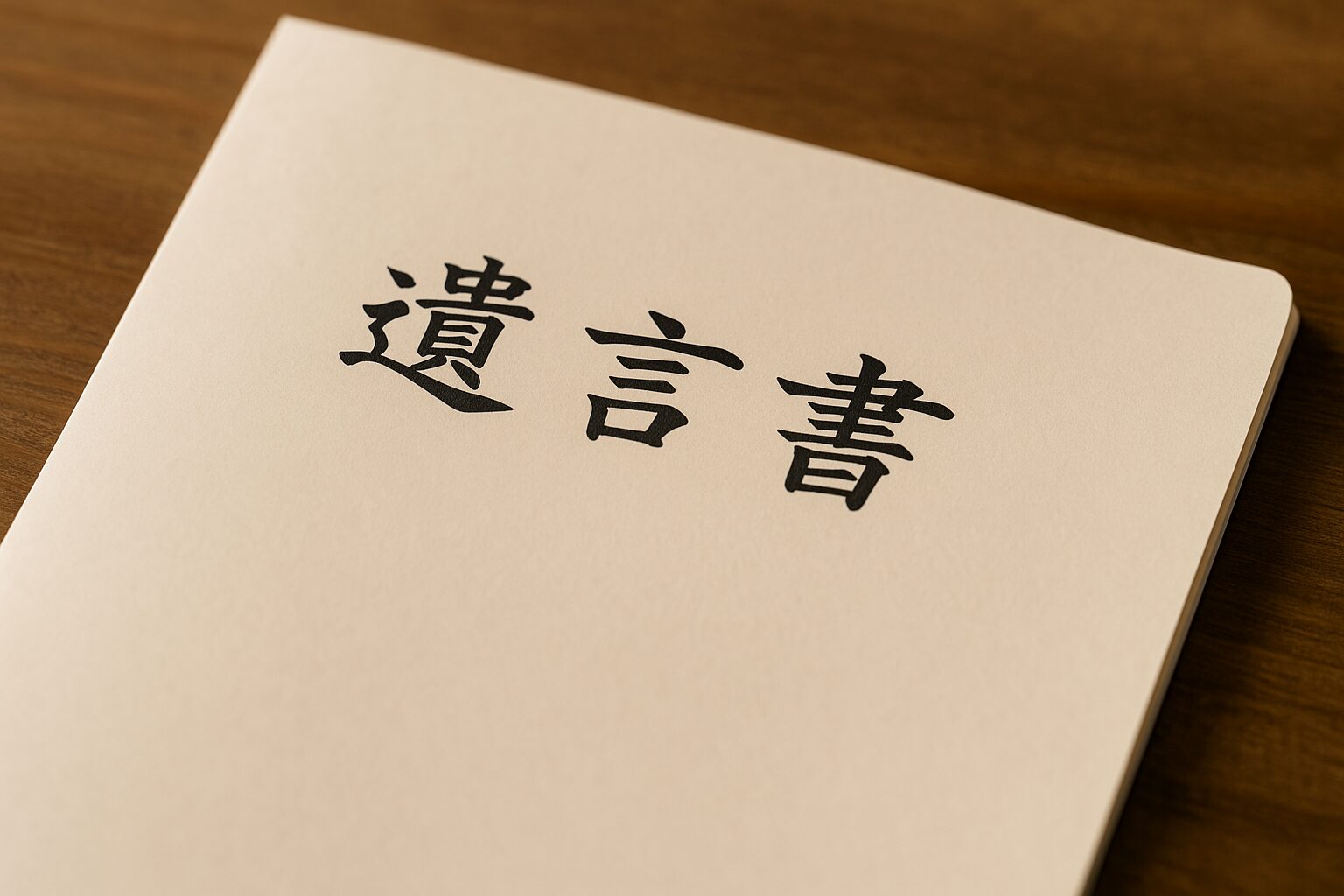
では、内縁の妻に財産を残したい場合、どのような方法が考えられるでしょうか。
代表的な方法に「遺言書」と「生前贈与」があります。
対策1 遺言書
最も確実な方法は、遺言書を作成して遺贈の意思を明示することです。遺言書があれば、法定相続人以外の人にも財産を渡すことが可能です。
遺言書の種類と遺言書作成のポイントは、以下のとおりです。
自筆証書遺言
自分で全文を手書きする方法です。費用はかかりませんが、形式の不備により無効となるリスクがあるため注意が必要です。
公正証書遺言
公証人役場で、公証人に作成してもらう遺言のことです。
公証人が関与するため、方式の不備で無効になる心配がありません。
また、原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクもありません。
裁判所の検認手続が不要で、すぐに効力を発揮できるという特徴もあります。
費用はかかりますが、最も安全で確実な遺言方法とされています。
遺言書作成のポイント
まず、内縁の妻に具体的にどの財産を相続させたいかを遺言書に明記することが必要です。
また、他の法定相続人の遺留分を侵害しないよう、財産全体を見渡してバランスを取ることが求められます。
対策2 生前贈与
生前のうちに、財産を内縁の妻に贈与してしまう方法も有効です。
たとえば、自宅を内縁の妻名義に変更しておけば、死亡後に相続争いになるリスクを回避できます。
ただし、生前贈与には、贈与税が課される場合があるため注意が必要です。
年間110万円までの贈与は非課税ですが、それ以上の金額を贈与する場合には高額な税負担が発生することがあります。
また、相続開始前3年以内の贈与は「相続財産に持ち戻し」されるルールもあります。
つまり、被相続人が亡くなる前3年以内に行った贈与については、その贈与分を相続財産に加えて計算されるのです。
内縁の妻に生前贈与で財産を残したい場合には、持ち戻しされないように計画的に行うことが必要です。
内縁関係の相続で直面しがちなトラブルと注意点

「遺言」や「贈与」で対策をしても、トラブルが生じるケースは少なくありません。特に他の相続人がいる場合は、感情的な対立も絡みやすいため注意が必要です。
トラブル例1 他の相続人からの反対と「遺留分」の壁
たとえば、被相続人に子どもがいる場合、子どもには「遺留分」が保障されています。遺留分とは、一定割合の相続財産を最低限確保できる権利です。
仮に、遺言で全財産を内縁の妻に渡すと書かれていても、子どもが「遺留分侵害額請求」を行えば、一部を取り戻される可能性があります。
トラブル例2 自宅や家財の所有権をめぐる争い
内縁の妻が住んでいた自宅が被相続人の単独名義だった場合、相続人が売却を希望すると、居住を続けられなくなるリスクがあります。
また、家具や家電といった家財道具の所有権も問題になります。
「生活を共にしていたから当然内縁の妻のもの」とは限りません。
家具や家電が被相続人の資金で購入された場合は相続財産に含まれるため、内縁の妻が単独で所有権を主張することはできません。
こうしたトラブルを避けるためには、遺言で居住権を明記したり、財産の分け方を具体的に記載することが重要です。
まとめ:まずは法律の専門家である弁護士へ

内縁の妻に財産を残したいという思いは自然なことです。
しかし、現行法では「相続権」が認められていないため、遺言や生前贈与といった特別な手段を講じる必要があります。
ただし、先に解説したところからもわかるとおり、遺留分や所有権をめぐって相続人との間でトラブルが起こりやすいことも事実です。
以上の点を踏まえると、内縁の妻に財産を残すためには、法律の専門的な知識が欠かせません。
想いを確実に実現するためには、まず弁護士に相談することが必要です。
長年支えてくれた大切な人に安心して暮らしてもらうためにも、早めの準備が何よりも重要です。
弁護士法人山本総合法律事務所は、相続の問題に知見が深く、内縁の妻に財産を残すための準備にも精通しております。
内縁の妻に財産を残したいとお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。