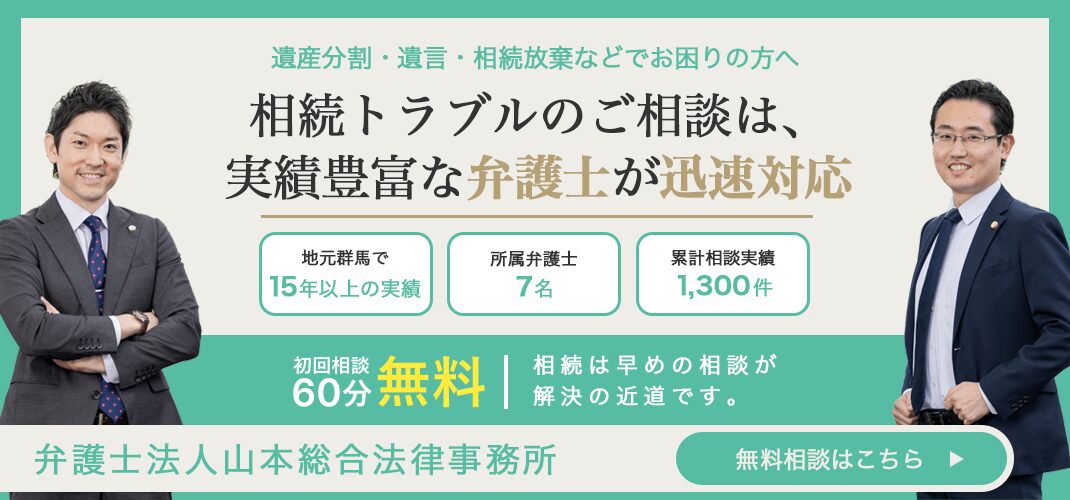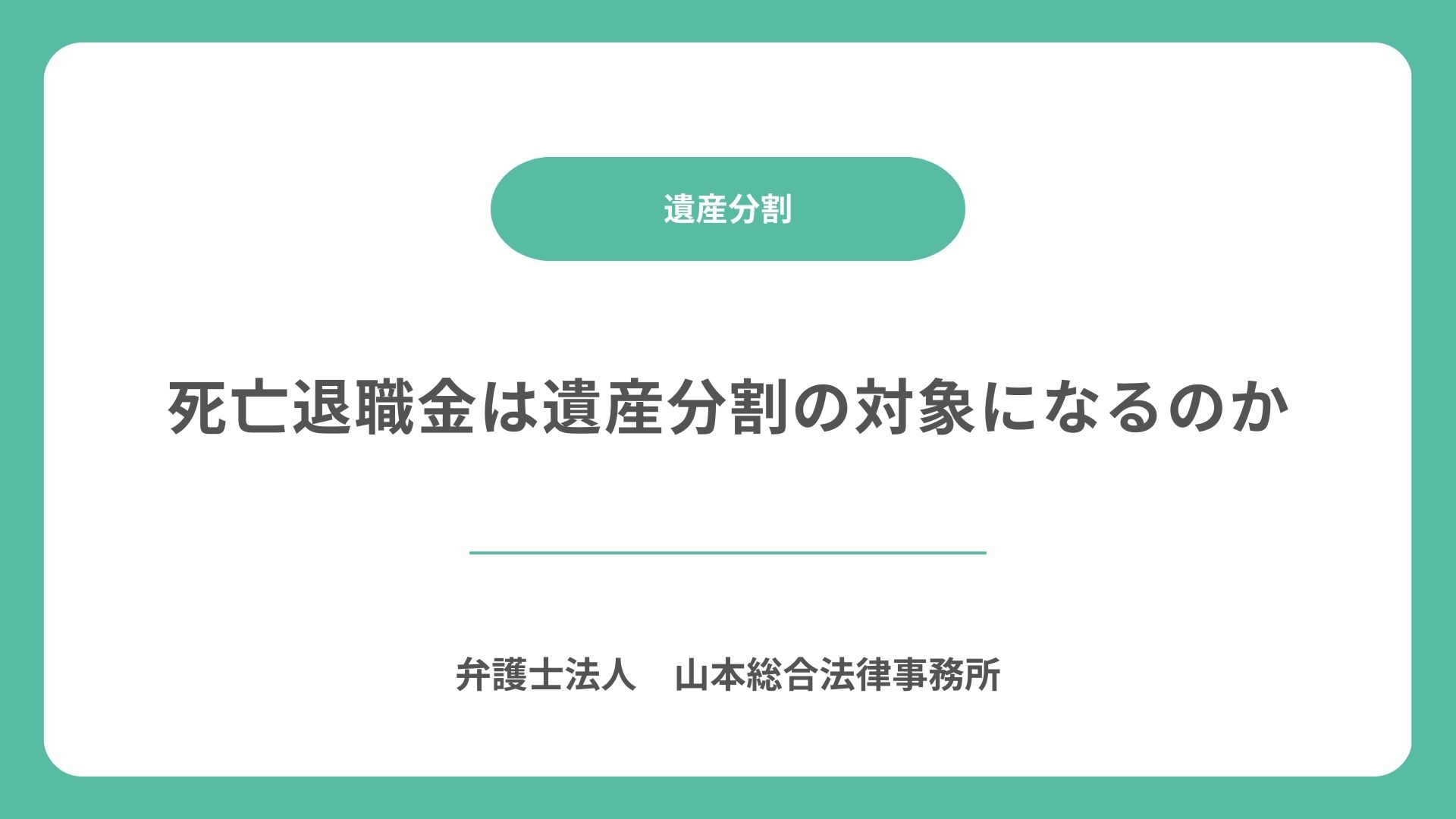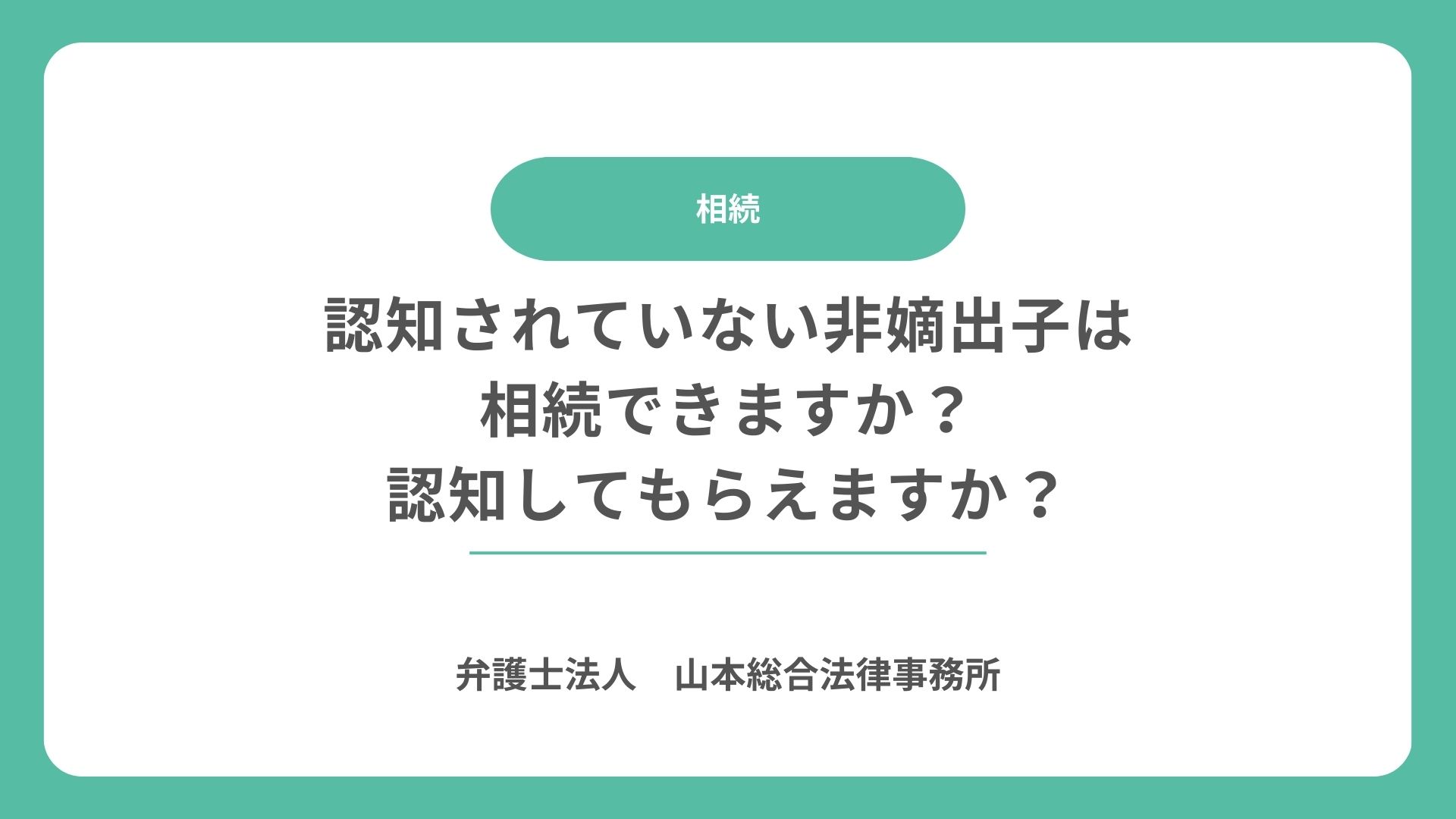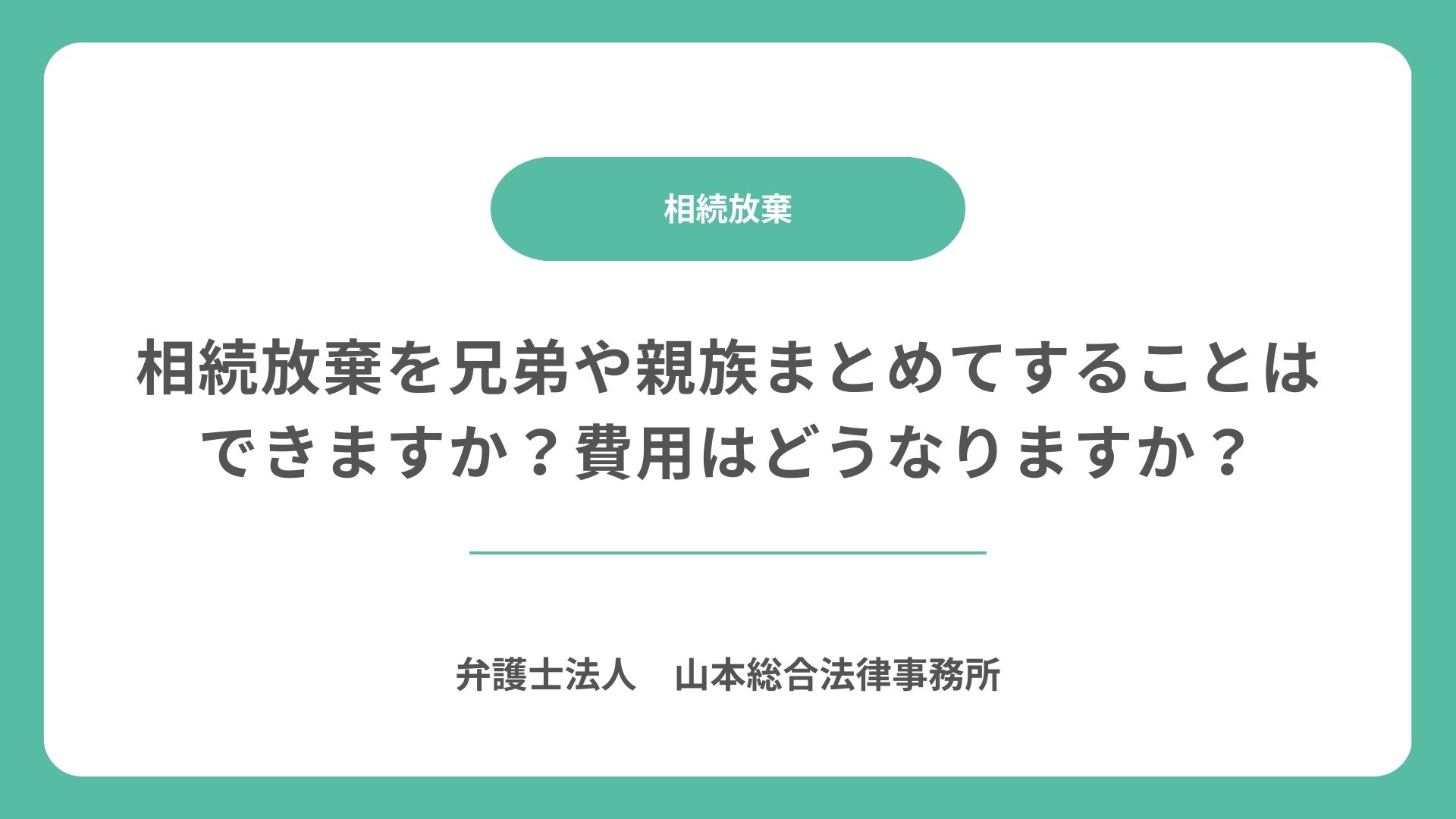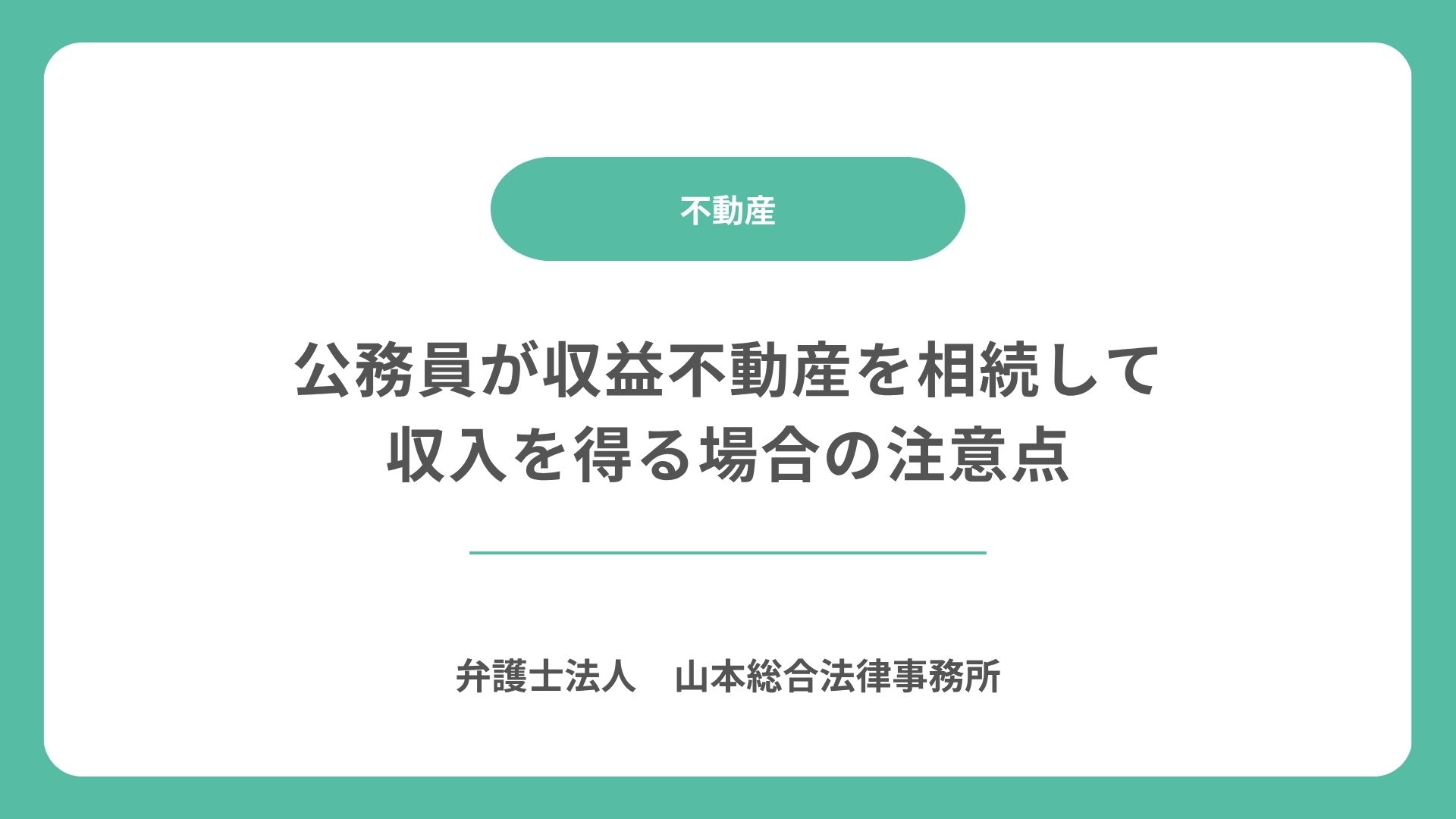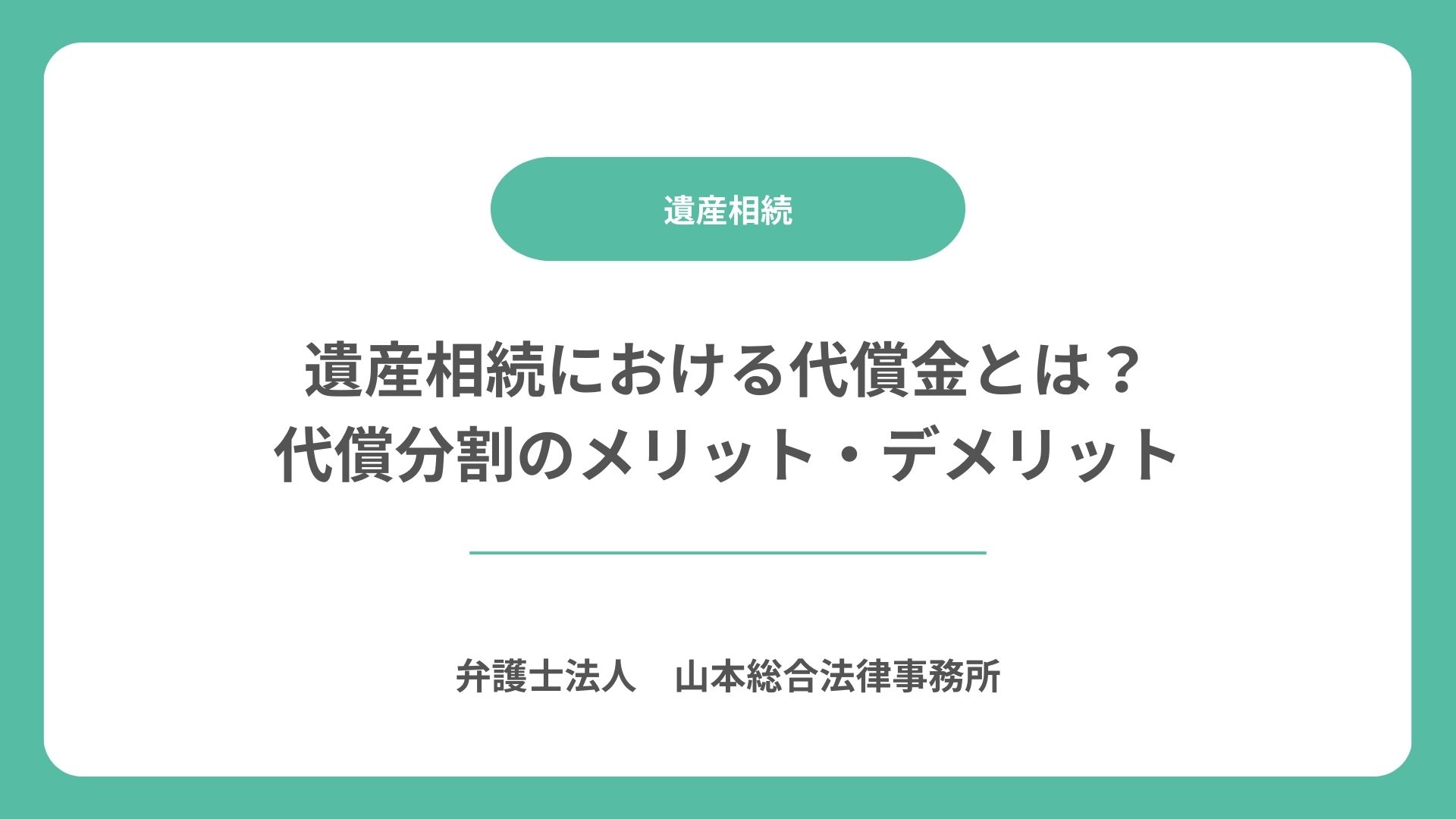- 公開日
- 最終更新日
【2025年版】生前贈与を検討中の方へ|失敗を防ぐために弁護士に相談すべき理由
- 執筆者弁護士 山本哲也
 高齢化が進むなか、相続を見据えて「生前贈与」を検討する方が増えています。しかし、制度をよく理解しないまま進めると、贈与が無効になったり、かえって税金が高くなってしまったりすることも。
高齢化が進むなか、相続を見据えて「生前贈与」を検討する方が増えています。しかし、制度をよく理解しないまま進めると、贈与が無効になったり、かえって税金が高くなってしまったりすることも。
本記事では、生前贈与の基礎知識から、よくある失敗例、弁護士に相談するメリットまでを、図や表も交えてわかりやすく解説します。
目次
1. 生前贈与とは?基礎から確認
生前贈与の定義
「生前贈与」とは、本人が存命中に、自分の財産を家族などに譲ることを指します。代表的な例としては、子どもに現金や不動産を渡すケースがあります。
贈与に関わる代表的な制度
生前贈与には贈与税がかかりますが、以下の制度を活用することで税負担を抑えることが可能です。
制度の一覧表
| 制度名 | 内容 | 非課税枠 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 暦年課税制度 | 毎年110万円までの贈与が非課税 | 年110万円/人 | 手軽だが継続性が必要 |
| 相続時精算課税制度 | 生前の贈与を将来の相続時にまとめて精算 | 最大2,500万円 | 相続時に税金精算される仕組み |
| 贈与税の非課税枠を利用した特例 | 用途に応じた非課税枠を活用して贈与を行う | 最大3,000万円(住宅)、1,500万円(教育)、2,000万円(夫婦間)など | 相続税対策に有効。一定の要件や申告が必要で、利用は原則1回限りのものもあり。 |
暦年課税制度とは?
「暦年課税制度」は、贈与税の基本的な仕組みで、毎年1人あたり110万円までは贈与税がかからない制度です。
-
1年間に贈与を受けた金額が110万円を超えると、その超過部分に贈与税が課税される
-
課税額は累進課税(受け取った金額が大きいほど税率が上がる)
💡 ワンポイントアドバイス|暦年課税制度
継続的な贈与による相続税対策として広く利用されていますが、名義預金と見なされないよう注意が必要です。
贈与の事実や受け取りの実態がないと、後に相続財産として課税される恐れがあります。
相続時精算課税制度とは?
「相続時精算課税制度」は、贈与時点では2,500万円まで非課税になる制度です。ただし、最終的には相続時にその金額を合算して税金を精算する仕組みです。
-
一度選択すると暦年課税制度に戻すことはできません。
-
主に「まとまった資金を早めに移転したい」ときに活用されます。
💡 ワンポイントアドバイス|相続時精算課税制度
一度選択すると暦年課税に戻れないため、将来の相続税額も見据えた長期的なシミュレーションが不可欠です。
贈与税の非課税枠を利用した特例とは?
目的に応じて一定額まで贈与税がかからない、特別な非課税制度です。以下のようなものがあります。
住宅取得資金の贈与(最大3,000万円まで非課税)
直系卑属(子や孫)に対し、住宅の購入資金として贈与する場合、一定の条件を満たせば、最大3,000万円まで贈与税が非課税となる特例があります。住宅の取得時期や家屋の要件などに注意が必要です。
教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)
30歳未満の子どもや孫に対して、教育費として信託口座を通じて贈与をする場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。学校や塾などへの支払いが対象となり、30歳に達すると制度は終了します。
※ 教育資金の一括贈与に関する特例は、期間限定の制度として設けられていますが、これまで何度か延長されてきた経緯があります。令和5年度の税制改正により、さらに3年間の延長が決まり、適用期限は令和8年3月31日までとなっています。
夫婦間の居住用不動産贈与(最大2,000万円まで非課税)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産やその取得資金を贈与する場合、基礎控除に加えて最大2,000万円が非課税になる制度です。適用は一度限りで、贈与税の申告が必要です。
💡 ワンポイントアドバイス|贈与税の非課税枠特例
住宅・教育・夫婦間などの特例はそれぞれ適用要件や期限、申告手続きが異なります。必ず事前に条件を確認しましょう。
まとめ
生前贈与は相続税対策に有効ですが、制度の選び方・使い方を誤ると損になることもあります。制度ごとの特徴を正しく理解して活用しましょう。
2. 生前贈与でよくある失敗と注意点

生前贈与にはさまざまな注意点があり、しばしば次のような失敗をしてしまうことがあります。
贈与が法律上成立していない
「この不動産をあげる」と口頭で伝えただけで名義変更をしないと、贈与が成立したとは見なされない可能性があります。
贈与契約は「意思の合致」と「履行」が必要であり、登記や契約書が重要です。
税務署から否認される
毎年110万円以下の贈与を繰り返しても、計画的な資産移転とみなされると相続税の対象になることがあります。
また、死亡前3年以内の贈与は原則として相続財産に加算されます。
家族間トラブルにつながる
一部の子にのみ贈与すると、他の相続人との間で「不公平感」が生じ、相続時に揉める可能性があります。
生前贈与は「特別受益」として相続財産に加算される場合もあり、遺産分割に大きく影響することがあります。
3. 弁護士に相談するメリットとは?

生前贈与を円滑かつ安全に行うには、法的な知識が不可欠です。弁護士に相談することで、以下のようなサポートが得られます。
メリット①:贈与契約を法的に有効にするサポートをしてもらえる
弁護士は、贈与契約書の作成や名義変更手続きなど、法的に有効な贈与が成立するようにサポートすることができます。
また、贈与後のトラブルを予防するための文書作成や証拠保全も行うことができます。
メリット②:将来の相続トラブルを防ぐためのアドバイスをしてもらえる
「この贈与は特別受益になるのか?」、「他の相続人から不満が出ないか?」といった視点から、遺留分や公平性に配慮した生前贈与の設計をしてもらうことができます。
弁護士は、相続トラブルの実例を多数知っており、具体的な予防策を提案できるため、この点のサポートをしてもらえるメリットは高いといえるでしょう。
メリット③:他の専門家と連携できる
不動産の登記や税務処理が必要な場合、弁護士は税理士や司法書士と連携して手続きを円滑に進めることができます。
必要に応じて信頼できる専門家を紹介してもらえる点も安心です。
4. 生前贈与にかかる主な費用

生前贈与には、以下のような費用がかかります。
主にかかる費用まとめ
| 費用項目 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 贈与額に応じて課税 | 財産の内容・金額による |
| 登記費用 | 不動産の名義変更 | 登録免許税+司法書士報酬 |
| 弁護士費用 | 贈与契約書作成・相談等 | 30分5,000円〜/契約書作成数万円〜十数万円 |
💡 ワンポイントアドバイス
相続税対策だけを目的に生前贈与を行うと、かえって税負担が大きくなることもあります。
制度の選択によっては、相続で受け取ったほうが税額が少なくなるケースもあるため、事前のシミュレーションが重要です。
贈与税のしくみを簡単に解説
生前贈与を行うと、財産をもらった人(受贈者)に対して「贈与税」がかかる場合があります。贈与税は、相続税とは別に課税される税金で、次のような特徴があります。
贈与税がかかるタイミングは?
原則として、1年間(1月1日~12月31日)の間に、1人から110万円を超える財産をもらった場合に、その超えた金額に対して贈与税がかかります。
贈与税の計算方法(暦年課税)
以下のように、受け取った財産の金額に応じて税率が決まっています。
| 課税価格(贈与額-110万円) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
💡 【計算例】
1年間に親から500万円の贈与を受けた場合、
500万円 - 基礎控除110万円 = 390万円 → 課税価格
→ 税率20%・控除額25万円 → 税額=390万円×20%-25万円=53万円
贈与税の申告・納付
贈与税がかかる場合は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに税務署へ申告・納税が必要です。忘れると加算税・延滞税が課されることがあるので要注意です。
登記費用とは?不動産を贈与した場合に必要な費用
生前贈与で不動産(土地や建物など)を渡す場合は、名義変更のために「登記手続き」が必要です。この手続きには次のような費用がかかります。
| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 法務局に納める税金 | 固定資産税評価額の2%(不動産取得税とは別) |
| 司法書士報酬 | 手続き代行費用 | 5万~10万円程度(事務所により異なる) |
💡 例:
固定資産税評価額が1,000万円の不動産を贈与する場合、
登録免許税=1,000万円 × 2% = 20万円
→ 司法書士報酬と合わせると、合計25万〜30万円程度かかるケースもあります。
登記を怠るとどうなる?
登記が完了していないと、法的には名義変更されていない状態です。そのため、
-
贈与が成立していないと見なされるリスク
-
将来的な相続争いの原因になる可能性
があります。不動産の生前贈与では、必ず登記を忘れずに行いましょう。
生前贈与に関するよくあるご質問(Q&A)
Q1. 生前贈与をすると、必ず贈与税がかかるのですか?
いいえ。一定額までは贈与税がかかりません。
「暦年課税制度」で毎年110万円までは非課税ですし、「住宅資金」「教育資金」「夫婦間」など目的別の特例を使えば、さらに高額でも贈与税がかからないことがあります。
Q2. 現金だけでなく、不動産も生前贈与できますか?
可能です。
ただし、名義変更のために登記が必要となり、「登録免許税」や「司法書士報酬」などの費用も発生します。贈与税の課税対象にもなるため、事前の準備と試算が重要です。
Q3. 子ども全員に均等に贈与しないと相続で揉めますか?
特定の子だけに贈与すると「不公平」と受け止められ、相続時に争いになることがあります。贈与が「特別受益」として相続財産に加算されることもあるため、バランスを意識した設計が大切です。
Q4. 贈与の証拠は残しておくべきですか?
はい、贈与契約書などの書面は必ず残しましょう。
口頭だけでは贈与の成立が認められなかったり、税務署に否認されたりするリスクがあります。
Q5. 弁護士に相談するのはどのタイミングが良いですか?
贈与を実行する前に相談するのが最も効果的です。
贈与の方法や税金、将来の相続への影響をトータルで見てもらえるため、不要なトラブルやコストを避けやすくなります。
5. まとめ|生前贈与はまず弁護士へ相談を
生前贈与は相続対策として非常に有効ですが、制度の選び方や実行の仕方を間違えると、税金面や家族関係で大きなトラブルを招くリスクがあります。
弁護士に相談すれば、以下のようなアドバイスが得られます。
-
何を、誰に、どのタイミングで贈与すべきか
-
トラブルを避けるための法的対策
-
他士業との連携によるワンストップ対応
弁護士法人山本総合法律事務所では、生前贈与に関する多数の相談実績があり、ご家庭の状況に応じたきめ細やかな対応が可能です。
「まだ早いかも」と思う段階でも、将来に向けたアドバイスが得られますので、ぜひお気軽にご相談ください。