生命保険金の持ち戻しを認めさせて遺留分として約1500万円を取得できた事例

ご相談内容
遺留分侵害額請求
解決方法
訴訟
相続人
Dさん(ご本人)を含めて5名
被相続人との関係
子
相続財産
不動産、預貯金、有価証券等
ご相談の経緯
Dさんの母が亡くなり、相続人はDさんを含めて5名でした。
相続人の1人が遺言執行者となり、公正証書遺言に基づき、遺言執行が行われました。
しかし、Dさんの取得した金額が遺産総額に比べて少ないのではないかと疑問に思われ、ご相談にいらっしゃいました。
遺言内容及び相続税の申告書を見ると、母が亡くなった後に発生した生命保険金の割合が大きい事が分かりました。
原則として、生命保険金は相続財産には含まれず、受取人に指定された人が全額を受け取れるものとされています。
今回のケースでは、相続人のうち一部の方が高額な生命保険金の受取人となっていました。
この生命保険金を相続財産に組み込むことができれば、遺留分として請求することが可能であると説明をしたところ、ぜひ請求をしてもらいたいとの要望がありご依頼となりました。
関連リンク:相続財産には何が含まれる?
関連リンク:遺留分を請求するには
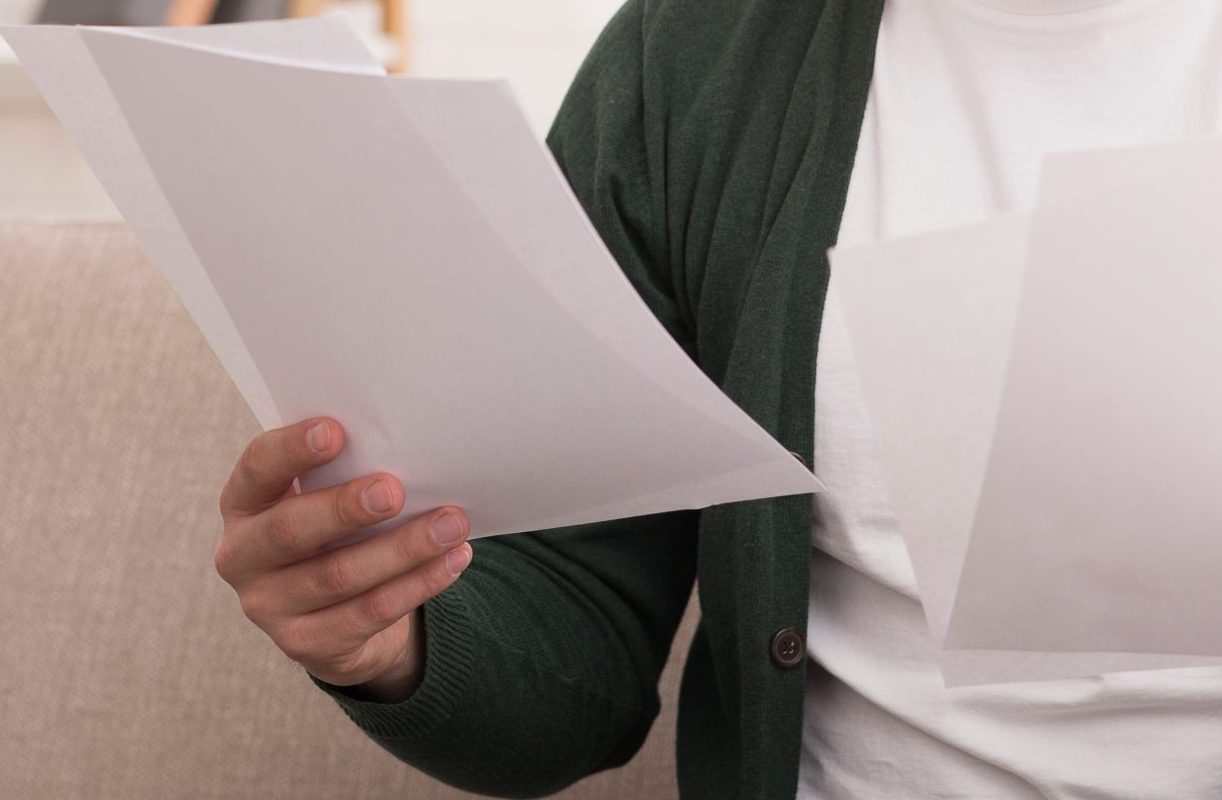
解決までの流れ
遺留分の請求を行うには、①調停、②訴訟が考えられます。
一般的には、①調停を申し立てた後、調停で解決ができない場合に、②訴訟による解決を検討するという流れとなります。
しかし、実務上、本件の争点である生命保険金は原則的には遺産に組み込むことができない性質であるため、①調停を申し立てたところで、話し合いの解決は困難なケースでした。
そのため、調停は申し立てず、すぐに訴訟提起を行いました。








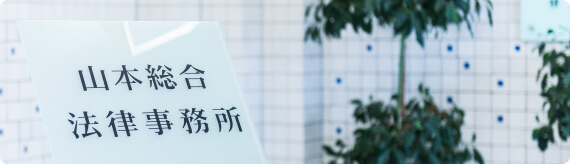


担当弁護士からのコメント
まず、訴訟提起にあたり、例外的に生命保険金を遺産に持ち戻した裁判例を調査しました。生命保険金を遺産に持ち戻す裁判例はいずれも遺産分割に関するもので遺留分に関する事例は見当たりませんでした。
しかし、裁判例で例外的に生命保険金を遺産に持ち戻す理由付けを確認すると、遺留分についても妥当するものであると判断しました。
(生命保険金が高額で相続人間で著しく不公平になってしまうケースについては、持ち戻しの対象となりえます。)
そのため、遺産分割に関する裁判例は遺留分も射程の範囲内であることを前提に、生命保険金が遺産に占める割合が高く、生命保険金を遺産に持ち戻して遺留分を算定しなければ、相続人間の不公平が著しいことを証拠に基づき詳細に主張しました。
その結果、裁判所において、生命保険金を相続財産に持ち戻すべきであるとの当方の主張が認められ、遺留分として1500万円の和解案が提示されました。その後、原告、被告らともに和解案を受け入れ、和解による解決となりました。
一般的に、生命保険金は遺産ではないため、遺産分割や遺留分の算定に考慮されることはありません。しかし、遺産に占める割合が多額の場合には例外的に算定に考慮される可能性があるので、疑問がある方は相続に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。
関連リンク:遺留分の基本 ~遺留分が認められる人、もらえる遺産の割合について~